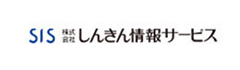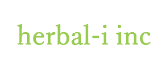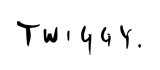ECサイト・ウェブサイト・ホームページの著作権を知ろう!専門の弁護士が注意点を解説
ECサイトなどのウェブサイトを運営している企業で、サイトの企画、構成、デザインなどを担当されている皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「自社のECサイトに関して、第三者と著作権をめぐるトラブルになるのは避けたい」
「そもそも著作権ってどんな権利で、どんな場合に侵害してしまうのか?」
「フリー素材と謳われていれば、使用しても問題ないのか?」
「消費者のレビューを広告に利用してもよいのだろうか?」
この記事では、ECサイトなどのウェブサイトにおける著作権の基本的な概念から、著作権に対する正しい理解を深め、法的トラブルを避けるための具体的なポイントをわかりやすく解説します。

-
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。EC企業からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行っている。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
目次
ウェブサイトの著作権の基本
ECサイトなどのウェブサイトにおける著作権の問題は、サイト運営者にとって事業を推進していくうえで非常に重要です。
著作権侵害は法律上の大きなリスクを伴います。民事責任の場合、差止や損害賠償を求められることが多く、特に企業にとっては経済的な損失だけでなく、信用の失墜にもつながります。さらに、著作権法に基づく刑事責任が発生することもあり、懲役や高額な罰金に科せられるリスクがあります。
まずは、ECサイトと、それ以外のウェブサイトの違いと、それぞれで問題となる著作権に関する事項について整理しておきましょう。
ECサイトとホームページの構造と目的の違い
ECサイトは、ウェブページの集合体であるという、広義の“ウェブサイト”の一種といえます。ECサイト以外のウェブサイトとしては、コーポレートサイト、ブランドサイト、リクルートサイト、ランディングページ(LP)などが挙げられます。業種を問わず、自社のコーポレートサイトやブランドサイトといったウェブサイトを持っている企業は多く、国内ではこれら自社ウェブサイトを、いわゆる“ホームページ”と呼ぶ場合もあるでしょう(以下、便宜上「ホームページ」といいます)。
ECサイトと、このホームページですが、その構造と目的に大きな違いがあります。まず、ECサイトは商品の販売を主な目的として構築されており、ショッピングカートや決済システムなど、購入プロセスをサポートする機能が充実しています。一方、ホームページは情報提供やブランド認知、コミュニケーションを主要な目的としています。そのため、ニュース記事やブログ、ブランドのコンセプトの紹介、企業情報などが中心となります。
著作権についても、サイトの構造と目的に応じて異なる注意点があります。例えば、ECサイトでは商品画像の著作権やレビューの著作権に対する対応が重要です。一方、ホームページでは文章や画像の著作権が主な焦点となります。
ECサイトとホームページの利用者の違い
次に、利用者の違いについて考えてみましょう。ECサイトの利用者は主に商品を購入しようとする消費者が中心であり、そのため使いやすさや商品の魅力を引き出す工夫が求められます。特に食品やクラフト製品など、デジタルマーケティングを活用して商品を魅力的に見せることが重要です。
一方、ホームページの利用者は必ずしも購買意欲の高い消費者に限らず、情報を探している人や企業のサービスを理解しようとしている人など多岐にわたります。したがって、幅広い情報を分かりやすく、かつ魅力的に提供することが求められます。また、サイトのコンテンツ更新やリンク・引用規定にも配慮が必要です。
このように、ECサイトとホームページはそれぞれの目的や利用者に応じた設計と運営が求められるため、著作権に関する管理も異なるアプローチが必要となります。
著作権侵害を避けるためのポイント
フリー素材の利用
ECサイトにおいて、商品画像の著作権は非常に重要です。商品画像は商品の魅力を伝えるための大切な要素であり、多くの場合、サイト運営者や写真家が独自に撮影したものが用いられます。このような商品画像は著作権法によって保護されており、無断転載や不正な利用は著作権侵害に該当する可能性があります。
著作権侵害を避けるための方法として、著作権フリー素材の活用があります。これらの素材は、著作権が制限されていないため、自由に使用することができます。ただし、フリー素材であっても、利用規約をよく確認し、条件に従って使用することが求められます。画像や音楽の素材を扱う際は特に慎重に対応し、著作権侵害を防ぐために信頼できるウェブサイトやプラットフォームから入手するのがおすすめです。
・EC事業者がフリー素材を安全に利用するためのガイド|リスク回避策
引用の適用
引用は、オリジナルの著作物を部分的に抜粋し、自分の作品に取り入れることですが、これは無制限に行えるわけではありません。著作権法第32条に基づき、引用が適法とされるためには、引用部分が従となり、自分の著作物が主となる関係であること、引用部分が明確に区別されていること、出所を明記することが必要です。こうした要件を満たさない引用は著作権侵害につながる可能性があるため、注意が必要です。
ちなみに、商品レビューもECサイトにおけるコンテンツの一部であり、これにも著作権が存在します。レビューは個々の消費者によって書かれたもので、投稿者自身がその著作権を持っています。このため、レビューを他のサイトや広告に使用する際には、投稿者の許諾を得る必要があります。
・EC事業者は注意!著作者の許可なく著作物を適法に利用する「引用」のルールとは
・EC・通販サイトに記入されたレビューは広告などに二次利用できる?
著作権譲渡契約
ウェブサイト制作を外注した場合、原則として、制作したクリエイター側に著作権が帰属することとなりますが、契約によりその権利を発注者に譲渡することも可能です。契約の中で著作権の譲渡に関する明確な取り決めを行うことは、将来的な著作権侵害のリスクを避けるためにも重要です。著作者人格権、共同著作などに注意し、権利の帰属について明確にしておきましょう。
・専門家が教える!外注でのシステム開発とWebサイト制作において契約書に定めるべき著作権の取扱いとは?
- ウェブデザインの著作権は誰のもの?
-
上記で触れましたが、ECサイトなどのウェブサイトを制作したら、そのサイトの著作権は、制作した人(企業であれば制作会社)に帰属します。
ただし、ウェブサイトと一言で言っても、具体的には画像、文章、動画、音楽といったコンテンツ、全体のデザイン、ソースコード、といった多くの要素が含まれています。
画像、文章、音楽といったコンテンツは分かりやすいと思います。著作権の保護の対象であり、他人の撮影した画像などを利用したい場合には、著作権へ配慮し、適切な許可を得て利用しなくてはなりません。
ソースコードも、3-1 著作権の保護対象となるソフトウェア・プログラム で後述しますが、著作権の対象となります。では、全体のデザインについてはどうでしょうか。結論から言うと、ウェブサイト全体のデザインも、著作物になります。
ただし、ウェブデザインの、レイアウトや配色は、一般的に著作物と認められません。
著作権法上の著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条第1項第1号)と定義されています。レイアウトや配色は、”創作的な表現”とはいえず、表現するための手段やアイデア、技法と解されるため、著作物とは認められないのです。
もちろん、そっくりそのまま真似をすれば、著作権侵害を訴えられる可能性がありますので、注意が必要です。このように、ウェブサイトの著作権については、適切な許可を得るなどの対応が必要であったり、解釈が複雑な場合があるため、必要に応じて専門家に相談しながら著作権侵害のリスクを低減していくことが推奨されます。
ソフトウェアやプログラムに関する著作権
著作権の保護対象となるソフトウェア・プログラム
ソフトウェアやプログラムに関する著作権は、著作権法の下で規定されており、その保護範囲が詳しく述べられています。プログラムは、著作権法第10条第1項第9号で著作物の一例として示されており、同法第2条第1項第10号の2で「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と定義されています。
注意が必要なのは、「創作性」がないプログラムは著作権法上の保護対象から外れていることです。また、プログラム言語、規約及び解法も(著作権法第10条第3項)著作権の保護対象外です。これは、例えばプログラム言語に著作権を認めると、これらの言語を使用すること自体が制限されてしまうからです。
複製と、例外
プログラムを利用する上で、データの消失や破損を防ぐためにバックアップをとることは必要なことです。著作権法では、バックアップのためにプログラムを複製する行為は認められています。ただし、自ら当該著作物を電子計算機において利用されるために必要と認められる限度とされています。(著作権法47条の3)特に企業においては、これを念頭にソフトウェアの複製管理を厳密に行い、著作権の遵守に努めることが求められます。
職務著作とは
自社で使用するソフトウェアやプログラムを、自社のスタッフが作成した場合、それらソフトウェアやプログラムの著作権はどこに帰属するのでしょうか。端的にいうと、原則として、スタッフ個人ではなく、会社に帰属するということになります。著作権法上の、職務著作という考え方が当てはまります。
職務著作とは、法人その他使用者(法人等)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物のことです。その法人等が自己の著作の名義のもとに公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、著作権はその法人等のものとなります(著作権法第15条)。これには著作者人格権も含まれます。
ポイントは「法人等の業務に従事する者」をどう捉えるかです。学説では、法人等と雇用関係にある者に限定されるとする見解と、雇用関係に限定されないとする見解で別れており、裁判所の判断に委ねられています。後々のトラブルを避けるためにも使用許諾の範囲やライセンス契約の内容を事前にしっかりと取り決めておくことが重要です。
リンクに関する法的問題
上述(2-2 引用の適用)のとおり、著作権法では「引用」の要件として、引用部分と自分自身の文章との区別が明確であり、引用の目的が適切であることが求められます。
特に文章が長い引用は注意が必要で、引用の範囲を最小限に抑えることが重要です。また、引用元を明確に示すことも、著作権侵害を避けるために必要なプロセスです。ECサイトや個人のウェブサイトであっても、基本的な著作権ルールをしっかりと理解し、適切に対応することが求められます。
その他知っておきたいポイント
ECサイトにおける知的財産権
知的財産権とは、創造的な成果やアイデアに対して与えられる法的権利のことを指します。
具体的には、本記事で取り上げている著作権の他、商標権、特許権などが代表例です。これらの権利は、創作者や企業が自らの知的創造物を独占的に利用することを認め、無断での使用や模倣を防ぐための法的な仕組みとして機能しています。
ECサイトにおいては、商品やサービスを提供する際に、これらの知的財産権を適切に管理することが重要です。無意識のうちに他者の知的財産権を侵害してしまう可能性があり、その結果、法的トラブルに発展するリスクも存在します。
著作者人格権
著作者人格権とは、著作者が持つ人格的利益を保護するための権利です。この権利により、著作者は自身の作品がどのように扱われるかを制御することができます。
著作者人格権には、作品の公表権、氏名表示権、同一性保持権などが含まれます。公表権は作品を公にするかどうかを決定する権利であり、氏名表示権は著作物を利用する際に自分の名前を表示させる権利です。同一性保持権は、著作物の内容を著作者の意に反して変更されないよう保護する権利です。
これらの権利は、著作権法により保護され、著作者の死後も一定の範囲で維持されます。重要なポイントは、この著作者人格権は、「著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」(著作権法第59条)ということです。
したがって、他人の著作物を使用する際は、これらの権利に注意を払い、必要に応じて著作者の許可を得ることが必要です。
共同著作物とは
共同著作物とは、2人以上の者が共同して創作した著作物で、それぞれの管理部分を分離して個別的に利用できないものを指します。
共同著作物においては、創作に寄与した人全員が著作者となり、著作権および著作者人格権が共有されます。共同著作物の著作権は共有となり、共有者はそれぞれの持ち分を有します。
共同著作物の共同著作者は、自分の持分を譲渡するなど処分したいときには、他の共同著作者全員の同意を得ることが必要になります。また、著作権を行使するためにも全員の同意が必要です。
こんな場合はどうなる?~事例紹介~
企業のWeb担当者による写真の無断使用
典型的な事例としては、ECサイトで使用される画像やテキストが挙げられます。他者の著作物を無断で使用するケースが後を絶たず、これが知らず知らずのうちにEC事業者の信用を損なう原因となっています。また、商品の説明文やコンテンツを自社サイトにそのまま転載した結果、著作権侵害に該当することもあります。
会社に所属するデザイナーが作成した制作物の著作権は?
では会社の業務として作品を制作した場合の著作権はどうなるのでしょうか?
上述したように、著作権法第15条に基づき、会社(法人)が著作者になることを職務著作といいますが、これに該当するには下記の通り4つの要件があります。
- 法人その他使用者の発意により、その指揮のもと著作物を制作すること
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成したもの
- 法人等の名前で公表されること(プログラムの著作物は例外。公表の要件はありません。)
- 契約や就労規則などでこの規定と異なる特段の定めのないこと
このように「職務著作」となるには、以上の4つの要件をすべて満たすことが必要となります。
逆を言えば、これらの条件を満たしていない場合は職務著作として認められない場合があるため、社内規定などに定めがあるか、確認しておきましょう。
著作権法違反の刑事罰
著作権法違反の刑事罰は、著作権法第119条に基づいて、次のとおり定められています。
・著作権、出版権、著作隣接権の侵害:
10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
・著作者人格権、実演家人格権の侵害:
5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
・有償コンテンツの違法ダウンロード:
2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
また、著作権侵害を行った者が法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者である場合は、当該法人にも最大で3億円以下の罰金が科されます。
著作権侵害は故意でなければ刑事罰の対象とはならず、過失による著作権侵害は刑事罰の対象外となります。著作権侵害には、刑事罰のほか、民事責任も科される可能性があります。民事責任としては、差止請求、損害賠償請求、名誉回復措置請求などが被害者から行われる可能性があります。
著作権侵害のリスクと対応
従業員研修
著作権侵害のリスクを回避するためには、まず社員の著作権に関する正しい知識の育成が不可欠です。著作権とは、著作物を保護するための権利であり、この権利を侵害すると法律的なリスクが発生します。したがって、著作権の基本的な概念、保護される範囲、利用時の注意点などについて、企業内で教育プログラムを実施することが重要です。特に、SNSを利用する機会が多い現代においては、インターネット上のコンテンツ利用に関しても慎重であるべきです。定期的な研修を行い、最新の法律情報や、著作権侵害の事例を取り入れることで、著作権侵害の予防に努めることが求められます。
その他にも対応のポイントについて、次に挙げる4点を確認しておきましょう。
その他
①著作権に関する知識を習得する
著作権の基本的な定義や種類について理解することが重要です。
今回の記事の内容や解説している書籍などから、基本的な内容を理解しておきましょう。
②利用する素材の著作権情報を必ず確認する
他人の著作物を使用する場合には、必ず著作権者からの許可を得る必要があります。
基本的には、著作権者との間で利用許諾契約を締結し、合理的な範囲内で著作物を使用することが求められます。
③著作権に関する契約書を締結する
著作者より著作物の利用許諾を受ける場合は、利用許諾契約書を作成し、著作権利用の範囲、条件、期間など具体的に記載します。そして契約範囲内で利用するようにしましょう。
④著作権侵害の疑いがある場合には、専門家に相談する
著作権侵害の際には専門家の助けを借りることが極めて有効です。著作権関連の法的手続きには専門性が求められるため、顧問弁護士や著作権に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。彼らは、侵害を主張するための法的文書の作成、裁判所への申し立ての手続き、さらには交渉などについて豊富な知識を持っています。これにより、法的なプロセスを順調に進めることができ、結果的に企業に対する著作権侵害のリスクと対応を適切に行うことが可能になります。
ECサイトにおける著作権についてのお悩み、リスク、課題は、解決できます
この記事では、ECサイトや自社ウェブサイトを持つ企業の皆さまが、これらウェブサイトを運営していく場合に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、ECサイトなどの企業ウェブサイトにおける、著作権をはじめとした専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「複雑で多岐にわたるECサイトの著作権の問題が、分かりやすく整理できる。」
「企業のウェブサイトにおいて、著作物を利用する際のリスクを最小限に抑え、企業としての信頼性を維持することができる。」
「著作権に関する法改定や新しいガイドラインについて、最新の情報に基づいたアドバイスを受けることができる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「自社サイトにおける、リンクの設定、引用について、改めて見直すことができた。」
「フリー素材について、利用規約をしっかり確認するなど、適切な利用方法が理解できて、安心して利用できるようになった。」
「著作者との間で必要となる、著作権譲渡契約や利用許諾(ライセンス)契約を適切に作成してもらえて、法的リスクを最小限に抑えながらスピード感を持ってビジネスを進めることができた。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の記載内容は、2025年3月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。