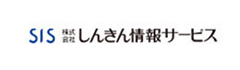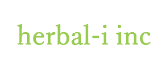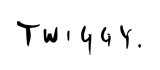他者と同じ商標を使用できる場合とは?|商標的使用について弁護士が解説
通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを運営する企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「ECサイトの商品説明欄で他社の商標と類似の商標を記載したいが、商標権の侵害になってしまうだろうか?」
「商標権の侵害について、事例で分かりやすく知りたい。」
「結局のところ、他人の商標権と類似の商標権を使用できるのはどのような場合・範囲なのか?」
この記事では、EC事業者が、ECサイト上で他者の商標と同一・類似の商標を使用しても、商標権侵害にならない場合についてEC専門の弁護士が詳しく解説します。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
目次
商標と商標権
商標とは、企業が自社の商品・サービスを他社のものと区別して認識させるために用いるネーミングやマークを指します。ブランドのロゴマークや、有名なお菓子の名前が想像しやすいと思います。商標法第2条1項には、商標とは人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音、その他政令で定めるものであって、①業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、②業として役務(サービス)を提供し、又は証明するものがその役務について使用するもの、と定義されています。
商標権とは、商標と、指定商品(使用する商品)・指定役務(使用するサービス)の2つの要素で構成されています。商標のみを登録することはできず、出願時には必ず使用する商品・役務を指定します。つまり、既に登録済みの商標を出願する場合であっても、指定商品や指定役務が登録済みのものと異なる場合には、登録ができる可能性があるということです。また、商標権を持つ者(商標権者)は、指定商品・指定役務について登録商標を使用する権利を独占的に有することになります(商標法第25条)。さらに、第三者が指定商品・指定役務に登録商標や類似する商標を使用すること、指定商品・指定役務に類似する商品・役務に登録商標や類似する商標を使用することをも排除する権利を有します(商標法第36条、第37条1項)。
次に、商標法の目的と商標権の機能についてです。商標権は商標法という法律により保護されている権利です。商標法では、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とすると規定されています(商標法第1条)。商標は、ビジネスにおいて自社と他社の商品・役務を識別するために用いることにより、次の3つの役割を果たしてくれます。この3つの役割を、商標の三大機能といいます。
・出所表示機能
同じ商標が付された商品やサービスは、いつでも一定の企業(生産者・販売者・提供者)によるものであることを示す機能です。例えば、カレー粉1つをとっても、消費者は何種類もの商品の中から、商品に付された商標を見て「これは自分の欲しい商品だ。」と認識し、購入をします。つまり、商標に係る商品・役務を提供する企業にとって、自社の商品・役務と他社の商品・役務を区別する役割が商標にはあるのです。
・品質保証機能
同じ商標が付された商品やサービスは、いつでも一定の品質を備えているという信頼を保証する機能です。商品・役務を提供する際に一定の品質を維持することにより、消費者からの信用や信頼を獲得します。品質の維持を長年にわたって積み重ねた結果、消費者が商標を見ただけで「このネーミングはこんなサービスだ。」「このサービスは信頼できる。」と確認できるようになるのです。
・広告機能
商標を広告に使用することで、その企業の商品・役務であることが消費者に伝わり、商品の購買・役務の利用を促す機能です。商品・役務の未利用者にとっては商標により商品・役務のイメージを印象深く残すことができ、利用者にとっては商品・役務の信頼をより深く印象付ける効果があります。
商標権の侵害と商標的使用
商標権の侵害の要件
商標法第25条には、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」と商標権の効力(独占的使用権)が規定されています。また、商標法第37条は、登録された商標やそれに類似する商標を、同一の商品・役務や、類似の商品・役務に使用することを商標権の侵害行為とみなす旨を規定しています(禁止権)。つまり、登録商標やそれと類似する商標を、指定商品・役務またはそれに類似する商品・役務について使用したことが、商標権侵害の要件ということになります。
しかし、前述の通り、商標と商品・サービスはセットで考えるため、商品だけが同一、商標だけが同一というだけでは商標権を侵害しているとはいえないケースもあります。以下に、商標権の効力について一覧にまとめましたので、ご参照ください。
| 指定商品・指定役務 | ||||
|
商標 |
同一 | 類似 | 非類似 | |
| 同一 | 専用権(25条) | 禁止権(37条) | × | |
| 類似 | 禁止権(37条) | 禁止権(37条) | × | |
| 非類似 | × | × | × | |
使用する行為の考え方としては、商品やその包装に商標を付す行為(商標法第2条1項)だけでなく、これらを譲渡・引渡し・輸出入・電気通信回線を通じて提供する行為も該当します。
商標的使用とは
商標法における商標権の基本的な侵害要件は前述した通りですが、実務上は、他人の商品・役務・商標と同一または類似の商標を単に使用しただけでは、商標権の侵害は成立しないとされています。ここで、商標的使用という考え方がポイントとなります。商標には3つの重要な役割があるとお話ししました。出所表示機能、品質保証機能、広告機能が商標の三大機能です。
これらの3つの機能の中で最も重要といえるのが、出所表示機能であり、商標がどの事業者のどのような商品・役務であるかを認識し、他社の商品・役務と区別をつける機能です。つまり、他者の商品・役務と識別できないような方法で商標を使用することは、出所表示機能の機能を損なってしまうため、商標権の侵害を行ったと認定される可能性があります。
以上のように、他者の商品・役務やその出所(企業)を識別できない方法により商標を使用する行為は、商標的使用といいます。商標的使用に該当するかどうかを判断するためには、①その商標表示の出所識別機能の強さ、②その商標表示がどの位置に表示されていたか、③ほかの商標が表示されているかどうか、についても総合的に考慮する必要があります。商標権者は、自らの商標が他社に使用されていれば、商標的使用に該当するか否かに関係なく警告文を送ってくるケースもあります。EC事業者は自らのビジネスを守るためにも、自己の商標使用が商標的使用に該当するのか、商標権者の商標権を侵害しているのか、弁護士や弁理士といった専門家の力を借りながら、適切に判断する必要があります。
- 商標権の使用権(専用使用権・通常使用権)について
-
本記事では、商標権の侵害と商標的使用について解説をしていますが、商標権者とライセンス契約(商標使用許諾契約)を締結することにより、商標を自由に使用できるようにする方法も考えられます。
ライセンス契約を締結する際には使用権の種類について検討しましょう。以下に、使用権の種類についてまとめましたので、ご参照ください。
・専用使用権
専用使用権は指定商品・指定役務に商標を独占的に使用することができる権利です。専用使用権が設定された場合には、商標権者さえも設定行為の範囲内において商標権を行使することができなくなる非常に強い使用権です(商標法第25条但書)。
上記の通り、専用使用権は非常に強い権利のため、ライセンス契約を締結するだけでは効力が生じません。専用使用権設定契約を行ったあと、その契約書を添付して特許庁に対して設定登録の申請を行い、はじめて専用使用権が成立するのです(商標法第30条4項、特許法第98条2項)。
・通常使用権
次に通常使用権とは、指定商品・指定役務に商標を使用することができる権利です。専用使用権とは異なり、商標権者は、自己の商標に通常使用権を設定しても、引き続き商標権を行使することが可能です。また、通常実施権は独占的な権利ではないため、複数の者に設定することもできます。
通常実施権の設定において、特許庁に対する設定登録の申請は不要です。しかし、通常使用権を移転したり、変更したり、処分等する場合には、設定登録を行わないと第三者に対抗できない可能性がありますので、その点にご留意ください。
商標におけるライセンス契約を締結する際には、ライセンス料やライセンス期間のほかにも、商標の表示方法(文字の大きさ・色等)や商標を付した商品・役務の品質保証についても明記することをお勧めします。商標使用に伴い、商標権者の企業イメージや商品のブランドイメージが毀損された場合には、損害賠償額が過大となる可能性もあります。繰り返しになりますが、ライセンス契約を締結する際には、専門家に適宜相談をしながら進めることをお勧めします。
商標権の侵害に該当しないと考えられるケース
・タカラ本みりん事件(東京地裁判例 平成13年1月22日)
しょうゆ、ウスターソース、ケチャップ等を指定商品とする「宝」「タカラ」といった文字表記(商標)を有していた原告が、被告が商品(魚つゆ)の容器に付したラベルの上から「タカラ本みりん入り」などと表記して当該商品を販売した行為が商標権の侵害にあたるとして、商品の販売差止を求めました。
裁判では、①当該商標を商品名として使用していないこと、②「タカラ本みりん入り」の表示は原材料・素材として表しているものであって自他商品を識別する機能を果たすような態様での使用はされていないこと、③原材料を通常の方法で表示する場合(商標法第26条1項2号)にも該当するため、商標権の効力が及ばないことを理由に請求が棄却されました。
商標法第26条には、商標権の効力が及ばない範囲として、商標権の効力が及ばない商標(商標の一部となっているものを含む。)を列挙しています。本ケースは、普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状等を普通に用いられる方法で表示する商標に該当するとして、同法第26条1項2号に該当しているとされました。さらには、前述した通り、「タカラ本みりん入り」に出所表示機能はないため、商標的使用とはいえないと考えることもできます。
商標権の侵害に該当しているかどうかを考慮する際には、下記の流れで検討していくことをお勧めします。
①他人の商品・役務・商標と、自己の商品・役務・商標が同一または類似であるかどうか
2-1 商標権の侵害の要件 の表をご参照ください。他人と自己の商品・役務・商標を当てはめて、専用権や禁止権の効力が及ぶ範囲である場合には、次の検討に進みます。
②商標を使用しているかどうか、その使用が商標的使用であるかどうか
一例ですが、以下のケースは、商標権の出所表示機能(自他商品識別機能)が果たされないため、商標的使用ではないと考え、商標権の侵害が否定される可能性があります。
- 自己の氏名・名称、著名な芸名等を普通に用いられる方法で表示する商標(商標法第26条1項1号)
- 普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法等を普通に用いられる方法で表示する商標(同法第26条1項2号、3号)
- 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標(同法第26条1項4号)
- 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもの(立体的形状、色彩又は音)のみからなる商標(同法第26条1項5号、商標法施行令第1条の2)
・EC・通販サイトを開設するなら、商標登録を検討しよう!
商標権のお悩み、リスク、課題は解決できます
この記事では、ECサイトの運営を行う企業の皆さまが、他者の商標を自社で使用した場合に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、EC事業における商標法、知的財産権についての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「自社の商品・役務が他者の商標権を侵害しているかどうか適切に判断することができる。」
「他社からの警告文や警告通知に対して、落ち着いて対応をすることができる。」
「自社の商品やサービスについての商標登録や商標の活用についての相談もできる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「自社の商品やサイトチェックと同時に、従業員に対しての法務研修もしていただき、担当部署の知的財産権についての意識が向上した。」
「相談をきっかけに自社商品の商標登録についても協力していただき、自社のブランド化の向上や事業拡大につながった。」
「分からないことや、そのまま進めてしまうと不安な点をすぐに相談できたので、自社の商品・サービスに自信を持つことができた。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の記載内容は、2025年3月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。