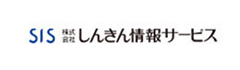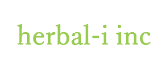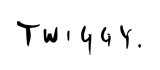越境EC事業で要確認の法規制|米国を中心にEC専門の弁護士が解説
通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを運営する企業の担当者の皆様は、越境EC事業の開始にあたって、次のようなお悩みがあるのではないでしょうか。
「国内EC事業から、越境EC事業へと販路の拡大が行われようとしているが、取引の相手方となる国の法規制について、社内でリスク管理がきちんとできるか不安に思う。」
「取引の相手方となる国の法律についてリスク管理をしたいが、優先順位はどのように考えたらいいのだろうか?」
「越境EC事業を行うにあたって、取引の相手方となる国の法律について詳しく把握するためにはどうしたらいいだろうか?」
「リスクを最小限に抑えつつ、自社の製品を海外展開させるためにはどのようにすればいいのだろうか?」
この記事では、越境EC事業を行う企業の担当者の皆様が特に注意したい法規制について、米国法を中心にEC専門の弁護士が詳しく解説します。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
目次
越境ECと法規制とは?
越境ECとは、インターネットを通じた国際的な電子商取引のことを意味します。つまり、ネットショップを通じて、国内から海外向けに直接販売をすることです。このような国際取引にも対応できるネットショップの開設方法としては、多言語対応の自社サイトを運営することや、Amazon(アマゾン)やebay(イーベイ)のような海外マーケットプレイスを利用することが挙げられます。
近年、EC市場は全世界的に成長しており、海外への販路拡大を狙う中小企業にとって、越境ECの活用は大きなチャンスにつながります。しかし、EC市場での製品販売には対面販売とは異なるリスクも存在し、対策を怠ると思わぬ損害を被る可能性があります。
特に、越境ECを行う場合には、日本だけでなく、海外のルールも十分に確認し、法的な準備を整えておくことが非常に重要です。
越境ECでは、他の種類のオンラインビジネスと同様に、ビジネスに適用される一般的な会社法および国内法および国際法を遵守する必要があります。さらに、ネットショップの運営では、Webアクセシビリティ、データプライバシー、および電子支払処理に関するデジタル固有の規定に準拠する必要があります。
- 契約にはどこの国の法律が適用される?
-
日本のEC事業者(A社)が米国の企業(B社)に対して自社の製品を売買するようなケースでは、日本法と米国法のどちらが適用されるのでしょうか。契約における権利義務につき適用される法律のことを準拠法といいます。日本の法の適用に関する通則法では、準拠法の選択について以下のように定められています。
・当事者が合意により自由に決める場合
例えば、A社とB社が契約を締結する際に準拠法についてあらかじめ合意しておくことが可能です。(法の適用に関する通則法第7条)もっとも、このケースではA社は日本法の適用を望み、B社は米国法の適用を望むことが一般的です。A社が契約締結を優先するために準拠法を米国法にするような場合には、A社はあらかじめ米国法について調査をし、自社にとって不利な点の洗い出し等を行う必要があります。・当事者の合意がない場合
当事者による準拠法の選択がないケースでは、法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法が準拠法となります。(同法第8条)「もっとも密接な関係がある地の法」の考え方については、2つの推定規定が設けられています。1つ目は、「片務契約の債務者の常居所地の法を、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する」というものです。たとえば、A社がB社に対してお金を貸付ける契約をしたようなケースでは、原則として米国法が適用されます。
2つ目は、「不動産を目的物とする法律行為については、不動産の所在地法を、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する」というものです。A社がB社に自社の不動産を売却する契約をしたようなケースでは、原則として日本法が適用されます。
準拠法については、黙示の合意が認められるケースも考えられますが、契約関係を明確にし、トラブルの発生時には迅速な対処ができるよう、契約書作成段階で明示的に取り決めされることをお勧めいたします。なお、準拠法は契約の性質や取引の態様、相手国の法律などにも影響されますので、契約書作成や交渉過程について、専門家に一度相談することも方法の一つです。
税金に関する法規制
消費税
消費税は州や市等の地域によって異なるものです。米国では45の州とワシントンDCが、州全体の消費税を課しています。そして、さまざまな市、郡、および「特別課税地区」においては、州全体の課税に加えて、地方の消費税率が追加される場合もあるので注意が必要です。 そのため、消費税額を適切に計算して徴収しないと、ECビジネスの利益率が低下する可能性があります。
輸入関税と税金
海外を拠点とするサプライヤー(ドロップシッピングプロバイダーや卸売業者など)から製品を輸入する場合、その輸入品は関税の対象となる可能性があります。 また、定期的に大量の製品を発送する場合は、他の関税や税金にも注意してください。
米国自由貿易協定(FTA)の取り決めを踏まえてそのシナリオを簡単に計算できるツールもあります。さまざまなシナリオをシミュレートしてみると良いでしょう。
その他に、顧客側が支払うべき税金も考えられます。なお、顧客側が支払うべき関税については、サードパーティロジスティクスプロバイダーが提供するプリペイドデューティシップを介して、一旦顧客の代わりに支払い、それらを上乗せした国際価格で顧客に販売することもできます。
環境税
持続可能性を促進するために、多くの州(米国)が環境に害を及ぼす可能性のある活動や品目に課税を導入しています。たとえば、California Redemption Value(CRV)法では、消費者は24オンス未満のプラスチック容器には0.05ドル、24オンスを超えるプラスチック容器には0.10ドルの追加のリサイクル料金を支払う必要があります。カリフォルニア州では、使い捨てプラスチックの中に詰められた個々の品目ごとに請求される新しい環境税の提案を保留しており、今後も同様の環境税が増えていく見込みです。
国際企業も進出先国の環境税に注意する必要があります。たとえば、ヨーロッパでは、持続可能でない製品、出荷、または梱包に対して追加料金を請求する案が審議されています。
支払いゲートウェイ
支払ゲートウェイとは、インターネットや実店舗での製品やサービスの最新の小売やその他のタイプの販売をサポートする電子商取引システムのことです。このシステムはECビジネスの基本となるものであり、「セキュリティ」対策には十分に注意する必要があります。例えば、顧客のクレジットカード情報などが漏洩すれば、損害賠償を求められることもあるでしょう。さらに、セキュリティ対策が不十分であると、ブランドイメージに間接的な損失も発生します。
したがって、支払処理業者の選択に関しては注意が必要です。そのため、以下のような認証を受けた信頼できる業者を利用するようにしましょう。
- PCI-DSSコンプライアンス
- GDPRコンプライアンス
- SSL証明書
- 統合されたセキュリティと不正防止保護
PCI-DSSコンプライアンスについて説明します。ペイメントカード業界データセキュリティ基準(Payment Card Industry Data Security Standard:PCI DSS)とは、クレジットカード会員の情報を保護することを目的に定められた、クレジットカード業界の情報セキュリティ基準です。2004年に国際カードブランドのAmerican Express、Discover、JCB、MasterCard、VISAの5社によって策定されたもので、現在も5社が共同設立した組織「PCI Security Standards Council:PCI SSC」によって運営・管理されています。
最新のeコマースプラットフォームには、通常、最高の評価である PCI DSS レベル 1 のコンプライアンスが組み込まれているものが多くあります。 実際に、アマゾン ウェブ サービス(AWS) は、最高の評価である PCI DSS レベル 1 のサービスプロバイダーとして認証を受けています。ただし、サードパーティの支払プロセッサまたは統合POSシステムを使用する場合は、PCIコンプライアンスの状態について、自身で確認することをお勧めします。
商標、特許、著作権に関する法規制
商標、特許、著作権は、米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office :USPTO)において、以下のように定義されているとともに、それぞれ法律によって保護されています。
- 商標:ある当事者の商品の出所を他の当事者の商品から識別および区別する単語、フレーズ、記号、および/またはデザイン
- 特許:発明の公開と引き換えに米国特許商標庁によって付与された、発明に関連する期間限定の財産権
- 著作権:具体的に表現された著作物、音楽、芸術作品などの著作物を保護するもの
ECビジネスにおいて、知的財産権の理解は2つの側面から重要です。
1つ目は、自身の知的財産に対して適切な措置を講じた場合、他のブランドが同意なしに自身の知的財産を使用することを防ぐ法的保護を受けることができます。
2つ目は、適切な同意なしに他者の知的財産を使用する際には法的なリスクを負うということです。たとえば、ディズニーやスター・ウォーズなどのキャラクターが描かれたTシャツを販売する場合は、法的な問題を回避するために相手側から適切な同意を得る必要があります。
また、販売する商品だけではなく、ECサイトそのものに対しても著作権侵害の有無を検討しなければなりません。例えば、カスタムeコマースプラットフォームのソースコードなどは、特許と著作権によって保護されます。他のECサイトのソースコードなどを勝手にコピーすることはできませんので注意が必要です。また、ロゴ、カスタムイラスト、ビジュアルコンテンツ(ソーシャルメディアへの投稿を含む)などECサイトのデザイン要素も、デジタル・ミレニアム著作権法(※1)などの著作権法によって保護されている場合があります。
※1 デジタル・ミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act :DMCA)
1998年に成立し、2000年に施行された米国の改正著作権法で、インターネット上の著作権侵害に対する罰則を強化しています。コンテンツをサイトに表示しているオンライン・サービス・プロバイダーが、著作権保有者またはその指定代理人から侵害の申し立て通知を受け取った際に当該コンテンツを迅速に削除した場合、著作権侵害の責任が免除されることを規定しているのが特徴です。
年齢制限に関する法規制
ECサイトを立ち上げるときには、例外なく、児童オンラインプライバシー保護法(Child Online Protection Act:COPPA)に準拠していることが必要です。この法律には様々な規制が含まれていますが、ECサイトに適用される可能性が高いのは、13歳未満の子供から個人情報を収集できないというものです。特に若い顧客層をターゲットにしているECサイトであれば、COPPA規制を遵守できているか十分注意してください。COPPA規制の違反事業者に対しては、最大43,280ドルの罰金が科せられる恐れがあります。また、カリフォルニア州プライバシー権法(California Privacy Rights Act: CPRA)は、その適用開始予定日が2023年1月1日からではあるものの、16歳未満の消費者(カリフォルニア州住民)の個人情報が無権限アクセス・流出・窃盗・開示の対象となった場合には、故意の有無を問わず、違反1件あたり最大7500米ドルの行政制裁金が課され得るという点で、改正前のCCPA(California Consumer Privacy Act)よりも厳格な内容になっています(CPRA1798.155(a))。
現在、世界では、児童や未成年者の個人情報の保護をいっそう強めていく傾向にあります。サイトの利用規約に簡易なチェックボックスを設置するだけでは、年齢確認や収集の同意を得たと認められない可能性もあり、ビジネス上このような情報を取り扱う場合には、細心の注意を払う必要があります。
ライセンスと許可に関する法規制
米国のほとんどの州では、実店舗で事業を行っている場合、販売者の許可が必要です。もっとも、オンラインビジネスでは、この許可の要否についての取扱いが異なります。ヘルスケアなどの規制された業界で製品やサービスを販売している場合を除き、オンラインでビジネスを行うために販売者の許可は必要ないことがほとんどでしょう。ただし、米国は州ごとにルールが異なりますので、適用される法律を常に再確認する必要があります。
また、販売許可とは別に、再販業者の許可証は検討すべき項目です。これは、消費税を支払うことなく、在庫をまとめて購入したり、卸売りしたりできるライセンスであり、所持することで二重課税といった金銭的負担増加を回避するというメリットが受けられます。つまり、再販業者の許可証を使用すると、顧客が製品を購入するときにのみ消費税を徴収すればよいことになるのです。同様に、卸売業者やサプライヤーと提携する予定がある場合は、地方自治体に確認することで、節税対策につながる可能性があります。
顧客のプライバシーに関する法規制
ECサイトでは、買い物客向けのデータ駆動型CXを作成するために、大量かつ重要な洞察を収集できます。しかし、世界には複数のデータプライバシー法が存在しており、分析目的で顧客の個人情報(氏名、住所、社会保障番号、デビットカードとクレジットカードの詳細など)を使用することを禁じています。
また、一部の州や国では、オンラインショップに対して、データの収集、保存、処理について顧客の許可を明示的に求めることが義務付けられています。
越境ECサイト運営で、特に注意すべきプライバシー法は以下の2つです。
- カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)
この法律は、消費者に関する情報、およびユーザーの要求に応じてデータが共有されるサードパーティのリストを開示することを企業に義務付けるものです。顧客は、プライバシー侵害について企業を訴えることもできます。
※2023年1月1日からは、CCPAの改正法(CPRA)が施行されているため、CPRAに対応した社内体制の構築(プライバシーポリシーの変更を含む)やその運用方法についても考えておくと良いでしょう。
- 一般データ保護規則(GDPR)
これは、EU加盟国全体の法律であり、顧客データの収集、保存、および使用に関して、オンラインビジネスが従わなければならない7つの必須の規制を定めています。
GDPRは、「最も厳しい顧客データのプライバシー」法として有名であり、違反の罰金は高額(2,000万ユーロまたは世界の収益の4%いずれか高い方)となります。
越境ECビジネスは、日本企業が海外進出、海外展開する際のよいきっかけとなり得ます。最近では、すぐにECビジネスを始めることができるようなパッケージも用意されており、海外市場に不慣れな日本の中小企業も参入しやすい状況です。
一方で、ビジネスの手軽さと自由度はイコールではないことには留意してください。越境ECビジネスでは、税金、支払いのセキュリティ、著作権、データの収集と使用など、様々な規制が関与します。
これらのオンラインビジネスに関する法律を理解することは、非常に煩雑に思えるかもしれません。しかし、法規制の知識は、法的な責任や損害賠償などのリスクからビジネスを守るためにも重要なポイントです。
たとえば、中国は市場が大きく、チャンスを掴みやすい反面、知的財産権が侵害されるおそれや、莫大な制裁金を課される(国内取引よりも負担増となる)可能性もあります。取引の相手方となる国の法規制をどこまで抑えられるかで、取り得るリスク防止策の幅は広がります。手軽に始められるからこそ、できる限りのリスク管理を行うことが、ECビジネスを末永く継続するカギです。
越境EC事業者に必要なインボイスの役割とは?|消費税・関税とインボイス制度についても解説
越境ECの法規制のお悩み、リスク、課題は解決できます
この記事では、EC関連サービスの企業の皆さまが、自社の商品の販路拡大のために、越境EC事業を開始する場合に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、越境EC事業を開始する際の支援、法令調査やリスクマネジメントついての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「越境EC事業を開始するにあたり、必要な外国法の規制についてきちんと理解ができるようになる。」
「損害賠償リスクの高い海外取引において、専門家がくまなくリスクを洗い出し、起こり得るリスクについて事前の相談や対策が可能になる。」
「法律以外のECビジネスの面からのアドバイスも可能なため、やりたいビジネス、理想とするビジネスにより近づける。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「研修を通じて、国内取引の経験しかない従業員の外国の法規制についての理解が深まり、日々の業務に活用できるようになった。」
「大きな局面だけでなく、通常の業務で生じた不安もすぐに相談ができるため、安心して自社の商品を海外に展開することができた。」
「取引国の法律の条文を一覧するだけでは把握できない、実務経験に基づいた専門的な観点からリスクを提示してもらい、より具体的にリスクを想定して越境EC事業を行えるようになった。」
「”やめておいた方がいい”ではなく、”どうしたらできるのか?””別の方法はあるのか?”という観点から寄り添ってくれたので、前向きな気持ちでビジネスを前に進めることができた。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
こちらから「メールでスピード相談」ができます。
※本稿の記載内容は、2025年1月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。