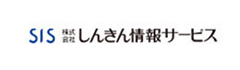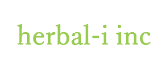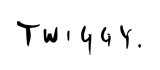通販サイトやオンラインモールなどのECサイトの開設を考えている企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「ECサイトの開設にあたって、どの業者とどのような契約を結べばいいのだろうか。」
「ECサイトの制作を制作会社に依頼したいが、料金やサポート内容を交渉できないか。」
「ECビジネスをする際に、各業者と適切に契約をするためにはどうすれはいいのだろうか。」
この記事では、ECサイトを開設・運営するにあたり必要となる契約と、各契約における注意点について、EC専門の弁護士が詳しく解説します。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
目次
ECサイト制作のための契約
制作会社との業務委託契約
サイトの制作会社とは、業務委託契約を結びます。注意すべきポイントは以下のとおりです。
・作業範囲をしっかり定義しておく
思わぬ作業で追加費用が発生するリスクを回避するために、どの作業までが料金内に含まれているのかを契約時点でしっかりと確認する必要があります。
・納品の流れを確認しておく
制作会社によっては、納品後数日の確認期間を設け、その期間を過ぎると修正不可という契約書を提示してくる場合もあります。気づかないうちに確認期間が過ぎてしまっていることがないように、納品の流れや方法は共有し契約書内に明記しておきましょう。
・修正への対応
サイトを制作してもらった際、問題点にすぐに気付けるとは限りません。ECサイトを運営していく中で、不具合が出てくることもあります。そんな時、修正に対応してもらえるかが重要です。中には修正対応期間を短く設定している・初回確認以降の修正は全て別料金という場合もあるため、確認しておきましょう。
・著作権の帰属
制作したサイトの著作権は、発注した自社に帰属するようにしましょう。契約書の内容によっては、著作権が制作会社側に帰属し、制作したサイト内の情報をパンフレットや他サイト等に二次利用することが制限される場合がありますので、注意が必要です。
たとえ契約書内に理不尽と思う内容があったとしても、その旨が記載されたまま契約を締結してしまったら、基本的にはそれに従わざるをえません。契約締結にあたっては、十分内容を確認し、必要に応じて相手方と交渉、擦り合わせをすることが大切です。
また、基本契約と個別契約に分けて契約を結ぶ場合には、作業範囲は個別契約にて締結することが多いため、個別契約もしっかりとチェックしましょう。
・【2024年版】ECサイト構築に利用できる補助金とは?
外部のECサイトを利用するための契約
ECサイト運営業者との運営委託・出店契約
ECサイトを運営するには、先述の、自社独自の販売システムを構築し自社ECサイトを運営する方法以外に、楽天市場・Yahoo!ショッピングなどの外部ECサイトを利用する方法もあります。どちらかを選択することも、T社長のように併用することもあるでしょう。
どちらにしても、外部ECサイトを利用する場合には、ECサイト運営会社と契約する必要があります。その場合、ECサイト運営業者とは個別に契約書を作成する必要はありません。基本となる申込フォーマットが準備されているため、その流れに従って申込手続きや登録をすることになります。
外部ECサイトへの出店の流れを、楽天市場を例にとって見てみましょう。
- 楽天市場の例
楽天市場への出店を検討している場合、まずは資料請求をして情報を確認することができます。資料請求をすると楽天市場の営業担当者から出店に関する連絡が来ることがあります。その際、出店料金(月々の固定費、オプション料金)・出店契約期間(更新・退店のタイミング)等出店後のサポート体制に関して、後のトラブルを避けるためにも、営業担当者とはメールでやりとりし、履歴を残しておくことが効果的です。楽天市場に出店する場合には、出店申込ボタンから必要な手続きを行います。手続きが完了するとRMS(楽天の店舗運営システム)が利用開始となり、実際に店舗ページを作成します。作成が完了するとオープン審査を経て、楽天市場内に開店できます。申込から開店までにかかる期間は1~2ヶ月が目安です。
(「開店までの流れ」(楽天市場)
(https://www.rakuten.co.jp/ec/open/?l-id=pc_header_nagare_open)参照)
- 利用規約とは?
-
サイト運営業者との契約において、個別に契約書を作成する必要はないことを前述しました。この場合、ECサイト運営業者との契約はどのように考えるべきでしょうか。出店者とECサイト運営業者の契約は、申込フォームなどにある、ECサイト運営業者の提示する利用規約に従って双方が法的に拘束されることになります。
利用規約と契約書の明確な違いは、契約書は双方で内容について協議、合意を行い作成される点に対し、利用規約はECサイト運営業者が一方的に提示をし、出店者が同意をすることにより利用規約の効力が発生する点です。また、契約書は取引の相手方によって個別に作成を行い、契約内容も相手方に応じて異なりますが、利用規約は画一的な内容であり、不特定多数の者との契約に用います。利用規約は性質上、契約締結場面で交渉をするというケースは多くありませんが、事前に内容を精査することでリスクを想定し、備えることが可能です。
一般的に、利用規約には民法の定型約款の規定が適用されます。定型約款は一定の要件の下、一方的に内容が変更されることがあるため(民法548条の4 1項)、変更時には変更内容や変更時期についてECサイト運営業者のホームページ等を確認されることをお勧めします。
商品販売ページにアクセスを集めるための広告代理店との契約
広告代理店との広告運用契約(業務委託契約)
広告代理店はそれぞれの代理店によって経験値やスキルにはかなり差があります。代理店を選ぶ基準としては、自社に近い規模・業態のECサイトに実績のある企業を選ぶと良いでしょう。
そして、広告代理店との契約は、広告運用契約や広告契約など、さまざまなタイトルが付けられていることがありますが、その内容としては、広告の運用を委託する、業務委託契約と考えられます。
リスティング広告の代理店を例にとって、契約時のポイントを紹介します。
・料金はある程度相場が決まっている
リスティングの代理店はかなりの数がありますが、料金に関してはある程度の相場があると考えていいでしょう。少額の場合は固定費、金額が増えてくると広告費の20%が一つの目安になります。
・契約期間は短く設定する
契約をする際の注意点としては、まずはお試し期間として契約期間を短く設定しておくことをお勧めします。リスティングの効果は1ヶ月、長くても3カ月程度で最適化することができます。その期間に効果を出してくれれば、契約を延長すれば良いのです。はじめから長い契約期間を必須とする契約には注意が必要です。
商品を仕入れるための契約
仕入先との売買契約
販売する商品ジャンルを絞ってECサイトを制作した場合にも、サイトで販売する商品をそろえるためには、数多くの業者との取引が必要になる場合があります。
取引をする仕入れ業者全てと、個別に売買契約を結びますが、売買契約を締結する前段階として、どの業者と取引を行うかに関しても慎重に検討する必要があります。特に、継続的に商品を提供してもらえるか・商品の原価はいくらになるか(掛け率)は重要です。
そして売買契約を結ぶにあたり、特に注意すべき項目は以下のとおりです。
・仕入れた商品に欠陥があった場合
仕入れた商品に問題があった場合、定められた期間内であれば返品・交換・損害賠償の請求ができます。これは契約不適合責任(改正前民法では瑕疵(かし)担保責任)といって法律で認められているものですが、売買契約の内容によっては期間が短い・売主の責任が限定されているなど、仕入れる側であるEC・通販事業者にとって不利な条件が設定されている場合があるため注意が必要です。特に期間に関しては、欠陥にすぐに気づけるとは限りません。販売後、しばらく経ってから返品されることも考えられます。そんな時に補償期間が過ぎてしまっていれば、自社で損害を負担することになってしまうのです。そのため契約不適合責任に関しては、特に期間・内容・範囲についてしっかりと確認しましょう。
・仕入形態
商品を仕入れるというと買取を思い浮かべる方が多いと思いますが、仕入形態には買取・受託・消化の3種類があります。
買取仕入:商品の所有権は買主に移ります。通販・EC事業者にとっては在庫リスクがありますが、利益は比較的多くなります。
受託仕入:商品の所有権を業者が有したまま仕入れをします。そして設定された期限に売れ残った商品を返品します。返品が可能なので在庫リスクがありませんが、販売手数料の設定が難しくなります。
消化仕入:商品が売れた際に仕入として計上され、会計処理としては買取と同様になります。販売されるまで帳簿上の在庫は存在しないので、通販・EC事業者の在庫リスクは低くなりますが、利益が比較的少なくなります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、仕入形態を決めましょう。そして、その内容が売買契約書に間違いなく反映されているかをチェックする必要があります。
その他にも、商品の発注から納品の流れ、新商品を取り扱い始める際の流れ、画像や商品情報の提供などに関しても、できる限り売買契約書内で取り決めておくとスムーズです。
商品を保管・出荷するための契約
運送業者との業務委託契約
運送業者との契約は口頭で行われることも多いですが、トラブルを回避するためにも書面で業務委託契約を結ぶようにしましょう。特に注意して契約内容に織り込むべきポイントは、以下のとおりです。
- 件数が増えた場合の料金割引
- 緊急の場合の追加料金
- 事故や遅延の場合の対応
- 出荷の方法(集荷か持ち込みか)
倉庫業者との賃貸借契約・業務委託契約
取扱商品が多い、もしくは大きい場合には、在庫を保管するために倉庫業者と契約をする必要があります。単純に倉庫の場所を借りる場合には賃貸借契約、在庫の管理まで依頼する場合には業務委託契約を結ぶことになります。
特に在庫管理を依頼する場合には、商品の管理方法について詳しく取り決める必要があります。JANコードで管理するのか・自社で発行した管理番号を使用するのか、委託商品の取り扱い方法、商品の破損などのトラブル対応、検品対応などに関して詳しく確認しましょう。また、ラッピング作業の可否、返品作業に関するコストについても確認しておく必要があります。
ECサイトの開設と運営で多くの業者と締結する「業務委託契約」と「秘密保持契約」のポイント
業務委託契約の注意点
この記事では、サイト制作会社、広告代理店、運送業者、倉庫業者との取引で、業務委託契約を結ぶ場面をご紹介してきました。
それぞれの取引の業務委託契約で共通して、特に検討が必要な事項は以下のとおりです。
・業務の具体的な内容
業務委託契約書には、委託する業務内容をできる限り詳しく記載します。委託した後にも関連する業務について依頼できるようにしておくと便利です。
・委託業務による成果物の帰属
委託した業務の成果がどの時点でどちらの当事者に帰属するのかをはっきりとさせておきます。例えばECサイト制作の場合、著作権がいつの時点で自社に移るかが重要になります。
・報酬に関する項目
業務委託契約書には、報酬に関する取り決めも必須です。どのような業務にいくらの報酬が発生するのか、それがいつの段階で発生しどのような方法で支払うのかというところまで、詳しく明記する必要があります。業務委託の場合には、報酬は委託した業務が完了した時点、つまり後払いになることが多いと思います。
・契約不適合責任
業務を委託する中で、何らかの問題が発生した場合の対応や請求できる手段、責任の所在をはっきりさせておく必要があります。
業務委託を検討する場合には、先方企業との間で契約に関する認識のずれを少なくすることが最も大切です。そのためには、自社の要望がしっかりと契約書に反映されているか、それを先方がしっかりと理解しているかを確認した上で、契約の締結に進むことが大切です。業務内容や委託方法が明確にされていないと、業務が完了した時や報酬を支払う段階で契約内容と違うといったトラブルになることも多くあるため注意しましょう。
・業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
秘密保持契約の注意点
秘密保持契約は、先方企業に自社の情報を開示する必要がある場合には必ず締結するようにしましょう。これは取引をするかどうかに関わらず、情報を開示するより前に締結する必要があります。
注意すべき点として、秘密保持義務を負うのが契約当事者双方の場合と、契約当事者一方のみの場合のケースがあるということです。きちんと自社の情報が守られている契約であるのかの確認は必須です。
また、情報開示の目的を明確にして目的以外での利用を禁じること、開示範囲をどこまで認めるか、秘密保持義務を負う期間に関しても注意すべき項目です。
秘密保持契約はとりあえず締結しておけば安心というイメージがあるかもしれませんが、自社の秘密が守られている契約なのか、そもそも秘密として扱われるべき情報は何かなどの視点を持って内容の検討を行うことが大切です。
ECサイトの開設に必要な契約のお悩み、リスク、課題は解決できます
この記事では、ECサイトの開設にあたって直面するお悩み、リスク、課題について、ヒントとなる基本的な知識をお伝えしました。これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、ECサイトの運営における契約審査、各種契約における予防法務についての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「必要な契約と、契約書のチェックポイントを抑えながら、ECサイトの開設を進めることができる。」
「各契約において想定されるリスクを洗い出し、業者や顧客とのトラブルを防止することができる。」
「不利な契約内容にならないよう、契約の場面において業者と適切な交渉を行うことができる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「分からないことはすぐに聞けるので、不安や疑問を放置せず、ECビジネスを進めていくことができた。」
「ECサイトの開設だけでなく、開設後の運営についても相談でき、法律を守りながらサイト運営をすることができた。」
「契約の締結場面において交渉することができたので、より自社の希望に適った内容で契約を進められた。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の記載内容は、2025年2月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。