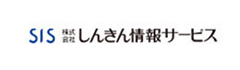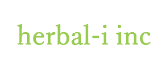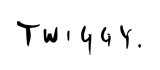他社のドメインに自社の商標を使われた場合は?商標とドメイン名の関係について弁護士が解説
通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを運営する企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「競合他社のホームページのドメインが自社の商品名と似ていて、ユーザーが競合他社のホームページに流入してしまっている。」
「自社の会社名と似ているドメインのサイトを見つけ、ドメインの使用を停止してほしいがどのように考えて、どのように対応すればいいのだろうか。」
「ECサイトの開設を考えているが、リスク管理のために商標やドメインについて対策をしておきたい。」
この記事では、ECサイトを運営する事業者が、他社のドメインに自社の商標が無断使用された場合の判断や対応についてEC専門の弁護士が詳しく解説します。

-
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。EC企業からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行っている。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
目次
ドメインと商標
当社はオリジナルブランド雑貨の販売をECサイトで行っており、オリジナルブランド名を商標登録しています。実は最近、ECサイトの売上全体が減少しまして、社内で検索・調査を進めていました。すると、競合他社であるB社が当社商標をホームページのドメインに使用していること、そのせいでユーザーがB社ホームページに流入してしまっていることが発覚しました。
当社としましては、B社に商標の無断使用を停止してもらいたいと考えていますが、B社のサービス名に無断使用されたわけでないため、どのように考え、対応をしたらいいか悩んでいます。
なるほど。今日はドメインと商標権についてのご相談ですね。まずは、ドメインについての概要と、ドメインと商標の考え方について解説します。
ドメインとは
ドメインはホームページやブログといったウェブサイトが、インターネット上のどこに存在するのかを識別するための住所の役割を果たします。「.com」、「.net」、「.co.jp」などが有名なドメインです。これらのドメインに、自社のサービスやブランド名などを組み合わせたものはドメイン名といい、ブログやホームページのアドレスはもちろん、メールアドレスなどにも使用されます。また、「○○○○.co.jp」の「.jp」部分をトップレベルドメイン、「.co」部分をセカンドレベルドメイン、「○○○○」部分をサードレベルドメインといいます。
同じドメイン名というものは存在せず、基本的には取得したもの勝ちとなります。ドメイン名には、サービス利用者にサイトを識別してもらい、サイトを覚えてもらいやすくする役割があります。ドメイン名を工夫することで、検索エンジンの上位に表示され、サイトへの集客アップ、売上アップを見込むこともできます。
ドメインは商標の侵害と判断できるか
まずは、ドメインへの商標使用が、①商標法上の標章の使用に該当するか、②標章の使用に該当する場合には、その使用が商標的使用(商標権の侵害)に該当するか、考える必要があります。
①について、商標法第2条3項には標章の使用の態様について定義されています。ドメイン名が標章の使用に該当する根拠として、商標法第2条3項8号に「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」と規定されている点があります。B社がホームページ上で商品やサービスの広告等を行っている場合には、それが電磁的方法(インターネット回線)により提供されているため、標章の使用に該当する可能性があります。
②について、商標権の侵害が成立するためには、標章の使用が商標的使用であるかどうかがポイントです。商標の三大機能として、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能があります。これらの機能を損なう態様によって商標が使用されている場合には、その使用が商標的使用と判断され、商標権の侵害が認められる可能性があります。
商標的使用に該当するかどうかを判断するためには、a)その標章の出所識別機能がどの程度の強さで表示されていたかどうか、b)その標章の表示位置、c)ほかの標章が表示されているかどうか、等も総合的に考慮する必要があります。
・他者と同じ商標を使用できる場合とは?|商標的使用について弁護士が解説
ドメインへの商標使用が商標権の侵害となった裁判例
ドメインと商標権の関係について、少し理解が深まりました!
それはよかったです。次は、ドメインへの商標使用が商標権の侵害となった事例をご紹介します。
■モンシュシュ事件(大阪高裁平成25年3月7日判決)
「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」という商標を有していたゴンチャロフ製菓株式会社が、株式会社モンシュシュに対して商標権の侵害として、使用の差し止め請求を行った事例です。株式会社モンシュシュは、自社のホームページのドメインに「mon-chouchou.com」を使用していました。ここで、ドメインの商標的使用が問題となりました。株式会社モンシュシュは「ドメインへの使用は商標的使用ではない。」と争いましたが、ウェブサイト上で自社商品の情報を提供し、注文を受け付けている実態を鑑みて、ドメインは株式会社モンシュシュの商品やサービスの出所識別標識としても使用されている、ドメインは商標的使用がされていると判断されました。
■日本知的財産仲介センター JPドメイン名紛争処理の事件・裁定一覧(2024年8月22日裁定結果実施)
株式会社NTTドコモが、「DOCOMO2.JP」のドメインを使用していた企業に対し、ドメインの移転を請求し、認められた事例です。この事例では、本件ドメインの主要部分は「DOCOMO」であり、株式会社NTTドコモのサービスを表す商標として著名な登録商標「DOCOMO」と混同を引き起こすほど類似していると判断されました。ここでも、出所表示機能を損なう点(商標的使用)が判断要素の1つになっています。
著名な企業の名称、著名なサービス名称のブランド価値を利用して自社のサイトに利用者を誘導するといったドメインへの商標の不正使用は、商標権の侵害だけでなく、不正競争防止法違反の問題となる可能性があります。不正競争防止法第2条1項に不正競争の定義が列挙されており、19号には「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」と規定されています。
自社の商標が不正使用されている状況を打開するためには、関係法令に則り、どのような対策が有効であるか精査することが重要です。自らのビジネスを守るためにも、弁護士や弁理士といった専門家の力を借りながら、迅速な対応を行うことをお勧めします。
- 日本知的財産仲裁センターとは?
-
「ドメインに使用されている標章と、自社の商標が商標法上の類似か非類似か判断が難しい。」「商標権の侵害について、スピーディーに解決したい。」「ドメインの登録取り消しや移転を行いたい。」といった場合には、日本知的財産仲裁センターに対して裁定の申立を行う方法もあります。
日本知的財産仲裁センターとは、日本弁理士会と日本弁護士連合会とが共催で運営する機関です。ドメイン名に関する紛争について、裁判所と日本知的財産仲裁センターの違いは判断の基準です。裁判では、不正競争防止法等の法律に基づく判断がなされる一方、日本知的財産仲裁センターではJPドメイン紛争処理方針(JP-DRP)に基づく判断がなされます。
仲裁とは、紛争の解決を仲裁人(パネル)に委ね、この仲裁人の判断に強制力を持たせる紛争解決手段です。仲裁判断には、裁判所の確定判決と同様の効力が認められるため、相手方が裁定結果の義務を履行しない場合には、裁判所の執行判決を得て強制執行を行うことも可能です。しかしながら、日本知的財産仲裁センターの裁定と裁判について、直接的な関係はないため、納得のいかない相手方から後に訴訟を提起され、2度手間になるといったリスクも考慮する必要があります。
他社のドメインが自社の商標と同一・類似である場合の対応
事例を教えてもらって、きちんと対処すれば、ドメインへの商標使用を止められることが分かって安心しました。
はい、次に、自社の商標がドメインに不正使用されていることが発覚した際の具体的な対策の手順について解説します。
商標権の侵害について検討する
貴社の今回のケースに当てはめると、まずはB社のサイトのドメインが貴社の商標権を侵害しているかどうかを検討することが重要です。B社が使用しているドメインが貴社の商標と同一又は類似しているだけでは直ちに商標権の侵害とは判断できず、B社の提供する商品・役務(サービス)も、貴社の商標の指定商品・指定役務と同一又は類似である必要があります。
証拠集め
商標権の侵害について検討すると同時に、証拠集めも積極的に行うことをお勧めします。訴訟を提起したり、日本知的財産仲裁センターに申立を行う場合には、自社の商標権が侵害されていることを自らが証明する必要があります。今回のケースでは、B社のサイトについて画像等で保存しておきましょう。また、自社の商標権を正式に証明するため、特許庁から商標の原簿を取り寄せておくことをお勧めします。
警告文の送付
相手方に対して、警告文を送付することも方法の1つです。警告文を送付する際には、一例ですが以下のことに注意しましょう。
■自社にきちんと権利があるかどうか
例えば、10年間の有効期限が切れていて更新を失念しているケースがないか確認しましょう。また、商標を登録しても、継続して3年以上当該商標を使用していない場合には、不使用取消審判の対象となり、反対に相手方から攻撃をされる可能性もあります。(商標法第50条)不使用取消審判を請求された場合には、商標権者(被請求者)が使用の証拠を出さなければいけません。
■相手方に先使用権が認められないか
具体的には、自社が商標登録を出願するよりも前に、相手方が当該商標を使用していて、その商標が相手方の商品・サービス名として有名になっている場合には、当該商標をその商品・サービスに限り使用することができる旨が規定されています。(商標法第32条)
■相手方にどこまで請求するのか
ただ単に使用を中止してほしいのか、これから解説する差し止め請求や損害賠償請求まで行うのか、企業として方針を固めておくことにより、警告文の作成、相手方の反応による今後の対応方針について検討しやすくなります。
差し止め請求
警告文を送付したにも関わらず、商標の使用が停止されない、警告文を無視されているといった場合には、使用の差し止め請求訴訟、損害賠償請求訴訟を提起することも方法です。相手方がホームページ上で当該商標の指定商品・指定役務と類似する商品やサービスの販売・広告等を行っている場合には、商標法第36条に基づいて差し止め請求を行うことが想定されます。
しかし、相手方のドメインが商標と類似しているにすぎず、ホームページ上では商品・サービスの販売や広告が行われていないケースも存在します。この場合には、商標法を根拠に差し止め請求を行うことが困難となるため、不正競争防止法第3条に基づき差し止め請求を行う、相手方ホームページで実際に商品・サービスが販売されることを待つことが想定されます。
自社の商標の無断使用のお悩み、リスク、課題は解決できます
当社としてすべきことはよくわかりました!しかし、商標権の侵害といえるかどうかの判断、法律を根拠とした警告文の作成、解決に向けた交渉といったことは、自社だけで円滑に進めるのは難しそうです。商標のドメインへの不正使用について、相談することは可能でしょうか。
もちろん可能です。商標のドメインへの不正使用が発覚した段階でご相談いただければと思います。商標権侵害の判断、警告文の作成、予防策のアドバイス、様々なことをお手伝いします。
この記事では、ECサイトの運営を行う企業の皆さまが、自社の商標を他社のドメインに無断使用された場合に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、EC事業における商標権とドメインについての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「他社のドメインが自社の商標と同一・類似である場合に、どのような問題があるのか、どのような対応ができるのか素早い判断ができる。」
「自社の商標を守り、価値を維持することができ、ユーザーからの信頼を獲得することができる。」
「法的な判断だけでなく、数多くのEC事業におけるトラブルを解決してきた事例を基にした具体的な解決策・ビジネス的なアドバイスを受けることができる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「他社のドメインへの商標の無断使用について、どこが問題なのか、どんなリスクがあるのか、何ができるのか、明確な対応を提示しもらえた。」
「法律的な問題点を指摘するだけでなく、具体的な対応や、法的対応以外のビジネスの実態に即した対応についても提案してもらえた。」
「素早い対応のおかげで、自社のホームページの流入数の減少を最小限にとどめることができた。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の記載内容は、2025年4月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。