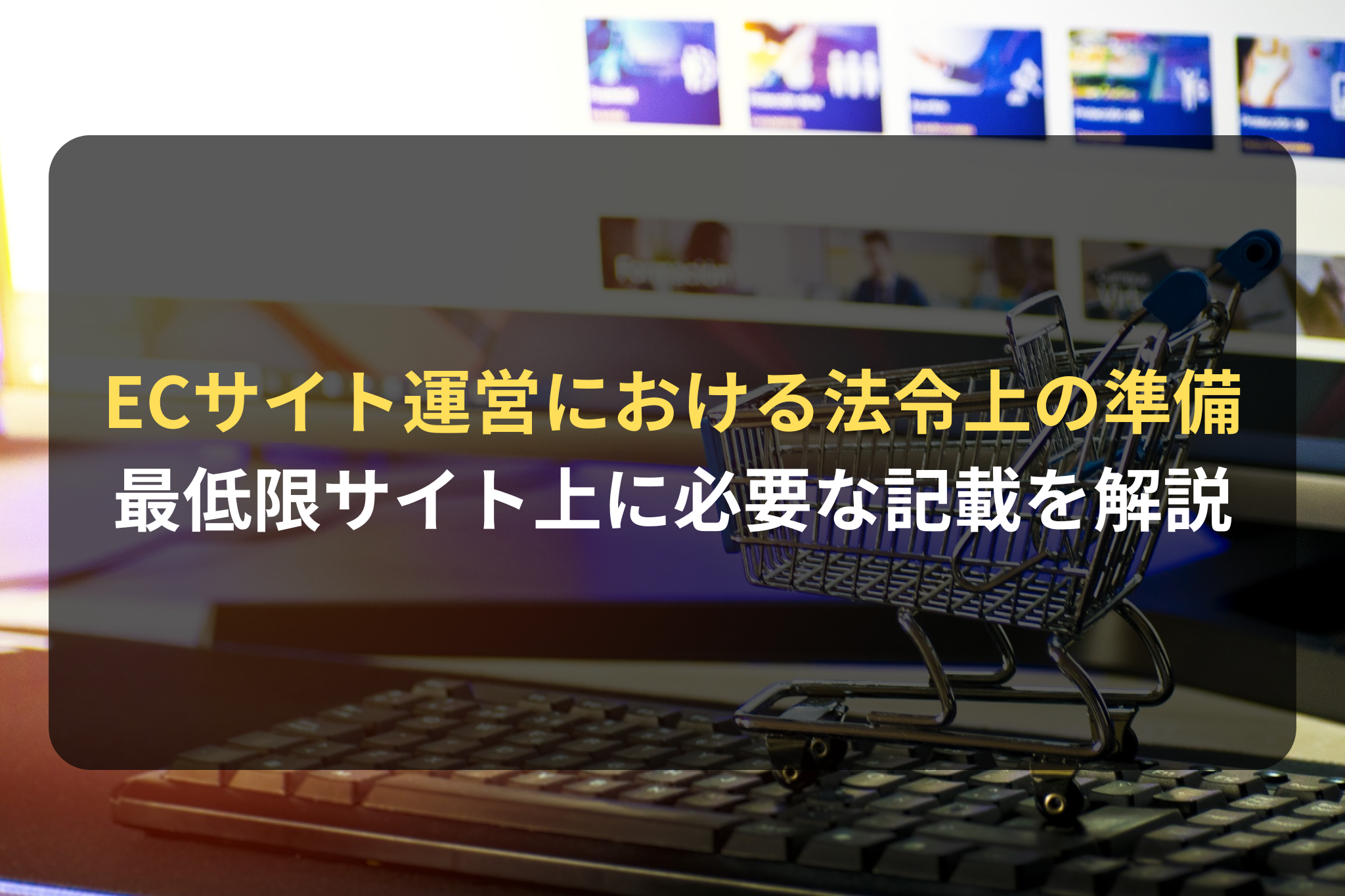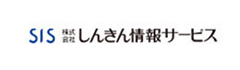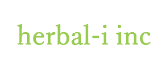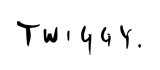ECサイトの運営において、法令上、事業者が準備しておくべきこととは?最低限、サイト上に必要な記載・表記を解説
通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを、これから立ち上げようとお考えの企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「ECサイト運営にはどのような法令が関係しているのか?」
「ECサイトの立ち上げの際には、法令上、何を準備しておけばよいのか?」
「ECサイトには、最低限、何を記載したり表記したりすることが求められるのか?」
「一度記載した規約などを変更したい場合は、どうすれば良いのか? 」
「自社サイトの記載事項が法令に違反しないようにするためには、どうすれば良いのか?」
この記事では、ECサイトの立ち上げや運営にあたって、事業主は、法令上、何を準備しておけばよいのか、また、最低限、ECサイト上に必要な記載や表記には、どのようなものがあるのかについて、EC専門の弁護士が詳しく解説します。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
目次
ECサイト運営に関わる法令
さらなる集客や売上増加、また、わが社のブランド力向上のため、amazonや楽天市場などのプラットフォームでの出品とは別に、自社で独自のネットショップを立ち上げたいと思っているのですが、どの法律のどのようなことを守ったら良いのか、簡単に分かりやすく教えていただけないでしょうか?
もちろんです。今回はECサイトの立ち上げと運営に関わる法令についての相談ですね。手始めに、ECとは何かについて、そして、ECサイトに関わる法令を把握しておきましょう。
実店舗を持たずウェブサイトを店舗として機能させ、物流網を利用し顧客に商品を配送することにより、ハード面での運営費用が抑えられるEC(Electronic Commerce:電子商取引)の市場規模は、近年、日本でも海外でも急速に拡大していることが市場調査のデータにより明らかになっており、新たなビジネス形態や消費体験として注目を集める存在となっています。
ECサイト運営に関わる法令は、ざっとまとめて一覧にしただけでも、下記の通りとなります。一見してその数の多さに驚かれるのではないでしょうか。自社サイトで扱う商品・サービスの内容により、古物営業法や薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)等、さらに他の法令の規制を受ける可能性もあります。
・民法
・特定商取引法(特定商取引に関する法律)
・消費者契約法
・景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
・個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
・資金決済法(資金決済に関する法律)
・通則法(法の適用に関する通則法)
・電子契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)
・特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)
・独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
・不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)
・プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
・預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)
・著作権法
・不正競争防止法 等
最低限、サイト上に必要な記載・表記は何か?
うーん、こんなにたくさんの法律を守らないといけないのですね。ちょっと自社ECサイトを立ち上げるのは想像以上に大きな高い壁が立ちはだかっているような気がしてきました。
確かに関係法令はたくさんありますが、最低限、ECサイトに記載・表記しなければいけない重要な事項は限られていますので、まずはそこを押さえて、あとは少しずつ進めていけば良いと思います。
ECサイトの立ち上げにあたり、まず最低限、サイト上の記載・表記に関する対応が必要なものは、下記の2点になります。
・特定商取引法に基づく表記
・利用規約の策定と公表
特定商取引法とは?
特定商取引法に基づく表記、インターネット上で見かけることはありますが、表記の意味や何を書けばよいのかについて、実はよく分かっていません。
特定商取引法とは、一定の類型の取引に対して、遵守すべきルールや消費者を保護するための規制が定められた法律です。特定商取引法においては、「通信販売」をする場合には、一定の販売者の情報を、運営するサイト上に一定の方法で表示しなければならないとされています。
表記の内容
特定商取引法では、「通信販売」を行う場合には、消費者トラブルを避けるため、下記の事項を「特定商取引法に基づく表記」として、消費者がすぐに分かるようにECサイト上に表示しなければならないとされています。
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
表記の方法
「特定商取引法に基づく表記」の表記の方法としては、一般的に、商品購入申込みボタンのすぐ近くや、ウェブページやアプリのトップページのフッター部分などの場所に、「特定商取引法に基づく表記」という文字に上記の事項が記載されたページのリンクを張るという方法が取られることが多いようです。
この方法による場合、その商品限定で該当する事項(代金等)については、リンク先ページでは、「商品ごとに記載」と表示し、それぞれの商品の購入ボタンがあるページに、商品毎に該当する事項を表示しておきましょう。ECサイトのデザインとの兼ね合いも考慮しながら、サイトを訪問した利用者にとって分かりやすい明確な表示とすることが重要です。
・ペナルティーやトラブルを防ぐ!ECサイトの特定商取引法に基づく表記とその書き方
改正特定商取引法のポイント
そういえば、特定商取引法は最近、改正されたと聞きましたが、概要について教えてください。
はい。2022年6月、2023年6月と相次いで改正特定商取引法が施行され、ECにおける新しいルールが導入されました。主な改正点は、以下の6つとなりますが、全てのEC事業者に影響する改正内容となっていますので、注意が必要です。
①最終確認画面における表示義務
②注文内容や契約の申し込み手続きに関して、消費者を誤認させる表示の禁止
③申し込みの撤回や解約をさまたげる不実の告知(嘘)の禁止
④消費者による注文の取消権を新設
⑤電話勧誘販売に関する規定の改正
⑥契約書面等の電子化
以下、それぞれの内容を確認しましょう。
①最終確認画面における表示義務
ECサイトにおける契約申し込みの直前の画面(以下、「最終確認画面」)に、商品の分量や販売価格、支払い時期・支払い方法、引き渡し時期、申し込み期間、申し込みの撤回・解除に関する事項を分かりやすく表示することが義務付けられました。それぞれの項目において、定期購入契約の場合は、その契約内容についても記載するよう求められています。
②注文内容や契約の申し込み手続きに関して、消費者を誤認させる表示の禁止
ECサイト最終確認画面に表示した注文内容や、定期購入等の契約申し込みの手続きに関して、消費者を誤認させる表示が禁止されました。購入手続きが完了することを消費者が容易に想像できないような表示も禁止となります。つまりは、法律で定められた項目をECサイトに記載すれば良いということだけではなく、消費者が契約内容を理解できるように表示することが必要とされています。
③申し込みの撤回や解約をさまたげる不実の告知(嘘)の禁止
消費者が購入申し込みの撤回や、定期購入の解約などを申し出た際に、その撤回・解約を妨げるために、事業者が事実と異なることを告げる行為が禁止されています。電話だけでなくメールも規制の対象です。
④消費者による注文の取消権を新設
ECサイトの最終確認画面に表示した注文内容(改正特定商取引法第12条の6で定められた6項目)が事実と異なったり、必要な内容が表示されていなかったりしたために、消費者が内容を正しく理解せずに(内容を誤認して)注文を申し込んだ場合、消費者は、その契約を取り消すことが可能と定められました。
⑤電話勧誘販売に関する規定の改正
従来は、特定商取引法で規定する「電話勧誘販売」の規制を受けずに、「通信販売」として扱われていた、消費者に電話をかけさせる方法(広告を新聞等に掲載する方法、テレビ放送、ウェブページ、SNS等)が、電話勧誘販売に該当する要件に追加されました。例えば、ウェブサイトの特定の商品についてコールセンターに電話をかけてきた消費者に対して、その商品以外の商品の購入を勧めたり(クロスセル)、定期購入を勧めたり(アップセル)した場合は、通信販売ではなく、電話勧誘販売に該当します。電話勧誘販売に該当する場合は、書面交付義務やクーリング・オフの適用など、通信販売の場合よりも厳しい規制を受けることになります。
⑥契約書面等の電子化
特定商取引法で書面交付が義務付けられている取引形態(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)について、デジタル化・ペーパーレス化という社会の要請に応え、消費者の事前の承諾を条件に電子化を認めることになりました。通信販売であれば、そもそも原則として契約書面等の交付義務はありませんが、上記⑤の電話勧誘販売に該当する場合は、契約書面や申込書面の書面交付義務が生じるため、要件を満たした上で電子化することが可能です。
特定商取引法の規制に今後も改正がある場合は、EC構築システムや運営のオペレーションに影響する可能性もあります。ECサイトの運営に関係する全ての法令やその改正等を網羅するのは、多大な時間と労力がかかるため、不明点などのご相談は、専門家にお気軽にお問合せください。
- クロスセル・アップセルとは?
-
クロスセル・アップセルとは、どちらも顧客単価を向上させるための営業ツールのことです。「クロスセル」とは、提供している商品とは別の商品も一緒に購入してもらうようにすること、「アップセル」とは、提供している商品より上位の商品やオプションも購入してもらうようにすることを指します。
クロスセルもアップセルも、どちらもその営業方法を用いること自体は違法ではありません。しかし、ECの通信販売において、クロスセル・アップセルを行う場合は、ECサイト上の表示の仕方や勧誘の方法に注意が必要です。例えば、消費者を誤認させるような方法での定期購入へのアップセルは、特定商取引法に抵触する可能性が高く、また、電話口で「不意打ち」的にクロスセル・アップセルの勧誘を行うことは、通信販売ではなく電話勧誘販売に該当する可能性が高く、通信販売よりも厳しい規制を受けると考えられます。
クロスセル・アップセルは、ECにおける売上アップのためには効果的な手法ではありますが、メリットとデメリットを考慮し、法令に抵触することがないよう、慎重な運用を心がけましょう。法令違反のリスクを下げるには、法律専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
利用規約とは?
特定商取引法については、よく分かりました!次に、利用規約の策定と公表もしなければならないのですよね?
はい、そちらも対応が必要です。利用規約とは、事業者が提供するサービスの利用に関するルールを記載したものです。以下で詳しく説明していきますね。
利用規約の記載事項(一例)
利用規約は、「約款」と同様、基本的に事業者が一方的に作成し、利用者に提示するものという特徴があります。利用者から同意を得られると、利用規約は契約の一部となり、利用者を法的に拘束します。
以下に、利用規約の記載事項の一例を紹介します。利用規約は、事業者が会員に提供する実際のサービスの内容に即して作成する必要があるため、利用規約を作成するうえでの基本的な留意点を押さえた上で、提供するサービスに合った内容にしなければならないことに注意が必要です。
- 利用規約への同意
- 用語の定義
- サービスの具体的内容
- サービスの利用料金と支払い方法
- 遵守事項
- 権利の帰属
- 利用規約の変更手続
- サービス提供の停止・終了に関する事項
- 損害賠償
- 反社会的勢力の排除
- 合意管轄・準拠法 等
利用規約は事業者が一方的に変更できる場合がある
サービス内容の見直しなどに伴い、利用規約の内容を変更したい場合があると思います。その際、変更前の契約者に対して変更後の利用規約を適用できないと、同様のルールによる管理という利用規約の目的が達成できません。
そこで、利用規約が「定型約款」(民法第548条の2第1項)に該当する場合、一定の要件を満たせば、利用規約の変更により、利用者の個別の同意がなくても契約内容を変更できるものとされました(民法第548条の4第1項)。一定の要件は、以下のとおりとなります。
1. 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
2. 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
・利用規約に関する民法の新しいルール、「定型約款」とは?
民法・消費者契約法に基づく利用規約の条項の無効に要注意
民法及び消費者契約法によって、以下のいずれかに該当する利用規約の条項は、無効とされてしまいます。利用規約を作成する際には、これらの事例に該当する条項が含まれないように、細心の注意を払い、規約全体を構成することが必要です。不安な点がある場合は、法律の専門家に作成や確認を依頼することをお勧めします。
・相手方の権利を制限する条項・義務を重くする条項であって、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの(民法第548条の2第2項、消費者契約法第10条)
・事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項
・事業者に責任の有無(損害賠償責任を負うかどうか)を決定する権限を付与する条項
(消費者契約法第8条第1項第1号、3号)
・故意又は重大な過失による事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項
・事業者に責任の限度を決定する権限を付与する条項
(同項第2号、4号)
・消費者の解除権(契約を解除する権利)を放棄させる条項
・事業者に、消費者が解除権の有無(解除権を持つかどうか)を決定する権限を付与する条項
(消費者契約法第8条の2)
・消費者が後見開始・保佐開始・補助開始の審判を受けたことのみを理由として、事業者に解除権を付与する条項(消費者契約法第8条の3。ただし、消費者が事業者に対して物品・権利・サービス等を提供することとされている契約を除く)
・消費者が支払う損害賠償の額を予定した条項・違約金を定める条項のうち、事業者に生ずべき平均的な損害額を超える部分(消費者契約法第9条第1号)
・消費者が支払う遅延損害金を定める条項のうち、未払額に対して年14.6%の利率を超える部分(同条第2号)
利用規約への同意の取り方
作成した利用規約を有効なものとするためには、下記の点に注意して、ECサイト利用者が利用規約に同意後に利用を開始できるようにする必要があります。
・ECサイト上に事前に利用規約を掲載しておく
・利用規約は、申込(または会員登録)より前に確認できる場所に配置する
・「利用規約に同意しました」チェックボックスや「利用規約に同意する」ボタン、「利用規約に同意して申込む」ボタンなどを利用して、確実に同意した上で申込や注文(または会員登録)に進めるようにする
・利用規約に最後まで目を通してからでないと、次に進めないようにする(利用規約の一番下に次に進むボタンを設置する、別リンクで利用規約を開いてからでないと次に進めないようにするなど)
・ECサイトの利用規約の作成方法とは?|知っておきたい注意点をECに強い弁護士が解説
ECサイト運営における法令上の準備についてのお悩み、リスク、課題は、解決できます
今日はありがとうございました。教えていただいたポイントをしっかりと踏まえた上で、ECサイトの立ち上げに必要な法令上の準備を行っていきたいと思います!
はい、応援しています。今日の内容を実際に活用して、法令を遵守したECサイトを立ち上げ、戦略的なマーケティングと両立させながら適切に運営し、貴社のビジネスのさらなる成長を実現させましょう!
この記事では、EC関連サービスの企業の皆さまが、新たにECサイトを立ち上げて運営していく場合に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、EC事業における広告表示、広告運用についての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「ECサイトを立ち上げる際に法令上、何を準備しておけばよいか明確になり、法令を遵守しながらビジネスを発展させられるようになる。」
「ECサイト上に記載や表記を求められる事項を正確に理解し実行することで、消費者に信頼されるウェブサイトの運営を実現できる。」
「特商法や利用規約に記載するべき事項や、ECサイト上での表示の仕方、改定の際の注意点を正確に理解でき、違法や無効となってしまうリスクを低減できる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「自社のECサイト上の記載・表記が関係法令に違反していないか確認してもらえ、自信をもってECサイトを立ち上げ、その後の運営もできるようになった。」
「特商法に基づく表記や利用規約に関する法令違反のリスクや適切な対応策についてのアドバイスをもらい、ECサイト増設や規約改定の際にも、適切に対応することができた。」
「ECサイト関係法令についてのセミナーや資料を通じて、従業員が法規制を理解し、業務に活かしてもらえるようになった。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
こちらから「メールでスピード相談」ができます。
※本稿の記載内容は、2025年1月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。