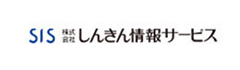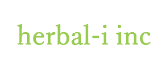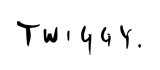転売対策なぜしない?理由と対策事例をEC専門の弁護士が徹底解説
通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを運営する企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「自社の商品がフリマサイト内で高値転売されるようになり、ユーザーが商品を手に入れられなくなってしまった。」
「転売された自社商品について、保証書がないにもかかわらず保証を求められる事案が続いており対応に困っている。」
「転売が消費者の信頼感、購買意欲の低下につながっており、転売対策を行いたいが効果的な対策が分からない。」
この記事では、ECサイトを運営する事業者が、転売対策をする際の注意点についてEC専門の弁護士が詳しく解説します。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
転売の定義と問題点
当社は、オリジナルキャラクターグッズを製造販売しております。この度、SNSの人気キャラクターランキングで当社のキャラクターが話題となりました。それに伴い、ECでの売り上げは増加しましたが、在庫が追い付かないこと、転売目的での購入が相次ぎ、従来からのファン離れを懸念しております。転売対策といっても、何から手を付けていいかも分からない状態です。
なるほど。今日は転売対策についてのご相談ですね。それでは、まずは転売の基本的事項と、企業がなかなか転売対策に踏み切れない理由について解説します。
転売とは?
一般的に転売とは、小売業が消費者に向けて販売している商品を買い取り、それをさらに他の人に販売することを指します。その際に、値段(販売条件)を変更し、転売業者は利益を得ています。転売の合法性ですが、結論からいうと転売という行為自体は原則として合法です。仕入れたものを販売するという行為は、市場経済の観点からも当然のことといえます。
転売の問題点
しかし、転売にはいくつかの大きな問題点があります。順番に解説します。
商品価格の不当な高騰
前述した通り、転売を行う際に値段を再度つけるため、商品価格が不当に高騰する(高額化する)ケースがあります。小売業者から消費者に販売されるという流通の流れに、転売業者が入るため、その分のマージンが上乗せされ、それを消費者が負担することになります。
消費者の不満感・不信感の増加
いままで必要な時に手に入っていた商品を買うことができなくなり、高値で転売されていることや、企業側の対策不足に対して不満感を抱く消費者が出てくることも転売の問題点です。また、あまりにも高額な転売が繰り返されることにより、企業ブランドや商品の使用されているキャラクターのイメージ低下、企業への不信感といったデメリットもあります。
公平な購入機会が失われる
転売の大きな問題点として、公平な購入機会が失われることが挙げられます。
なぜなら、転売の対象は、生産者が設定した価格に対して需要が大幅に上回る、数量・期間限定の人気商品や、災害時の不足物資などに集中するからです。
転売業者は、こうした商品を買い占めて不当に価格を吊り上げます。その結果、本当に商品を必要としている消費者は、定価で買えなくなったり、不本意ながら高額で購入せざるを得なくなったりします。
そして、その上乗せされた利益は、商品の生産者や正規の販売元には一切還元されず、すべて転売業者のものになってしまうのです。
転売対策が難しい原因
転売の問題点について解説しましたが、ここまでお話すると「どうして企業はもっと転売対策をしないのか?」という疑問が出てくることでしょう。次は、転売対策を容易に行うことが難しい原因について解説します。
過大な対策コストがかかる
転売対策には過大なコストがかかることも珍しくありません。たとえば、不正な購入を検知するシステムの導入や転売業者をあぶり出すための規制を行うには、システムに対するコスト、ルール整備に関するコスト、人的なコストがかかります。転売対策を行うことで企業にとってはブランドイメージの維持、消費者からの信頼獲得、自社製品の適正価格の維持といったメリットはあるものの、簡単には踏み切れない現状もあります。
購入ハードルが高くなり販売機会を逃す
たとえば、転売業者をはじくために、販売するゲーム機に最低プレイ時間の制限や、一定の認証手続きを設けた場合、消費者は「以前は無条件で購入できていたのに。」と不満に思うかもしれません。また、中には「面倒なのでもう少し後になってから購入しよう。」と購入することをあきらめてしまう可能性があります。転売対策を行ったことにより、消費者の購入ハードルが上がってしまい、結果として企業側が想定していた販売機会を逃してしまうこともあるのです。
転売対策が法令上制限されるケースも
企業側が転売対策を行った場合に、その対策自体が法律違反となるおそれもあります。たとえば、メーカー側が再販売価格に制限を設けた場合はどうでしょうか。メーカーとしては再販売価格を決めてしまえば、転売によって不当な価格高騰を防止できます。しかし、例外はあるものの、再販売価格の拘束は独占禁止法によって禁止されています(独占禁止法第2条第9項第4号参照)。
その他、転売業者と思われる者のリスト一覧を作成するといった対策も、個人情報保護法の利用目的による制限(個人情報保護法第18条参照)、適正取得(同法第20条参照)の観点から制限される可能性があります。対策する企業側も各種法令に拘束されることになるため、容易に転売対策ができないのです。
実際の転売対策事例
転売による企業側へのダメージは大きいのに、転売自体は合法なんですね。なにかいい対策はあるのでしょうか。
転売対策については、様々な会社が新しい試みを行っています。実際の転売対策の事例をご紹介します。
任天堂スイッチ2
まずは、任天堂株式会社が任天堂スイッチ2の販売に際して講じた転売対策をご紹介します。
保証サービスを利用する際は領収書が必須に
修理サービス規定、保証規定を制定することにより、無償修理を依頼する場合には保証書のみでなく、商品購入時のレシート、領収書、納品書等の購入証明書も添付することが必要になりました。また、任天堂スイッチ2には、保証書自体が存在しないのです。
任天堂スイッチ2の無償修理を依頼する場合には、購入証明書が必須となります。しかし、転売品には購入証明書が添付されていないことがほとんどです。それは、購入証明書には、購入者の氏名・住所といった個人情報が記載されているため、転売業者は購入証明書を添付できないのです。購入証明書がなければ、初期不良に対応ができず、転売業者から高値で購入したにもかかわらず、追加の費用が掛かってしまう可能性があります。
上記のように、転売によって商品を手に入れたとしても、デメリットが生じる状態を作り、転売業者からの購入を抑止しているのです。
フリマサイトに協力を依頼
2025年5月27日付で、任天堂と、フリマアプリを運営するメルカリ、LINEヤフー、楽天グループの3社は任天堂の商品について、不正な出品行為を防止する取り組みに協力することを合意しました。利用規約に違反する不正な出品行為に対して、3社は能動的な出品削除対応や、情報共有を含む連携体制の構築をすることで、転売業者の出品自体に歯止めをかけることが期待できます。
ユーザーへの積極的な情報公開
消費者に積極的に販売時期、販売情報をアナウンスすることにより、消費者が販売時期を把握できる仕組みを構築しています。スイッチ2は2025年6月5日の販売開始でしたが、2025年1月16日時点で販売情報について公式HPで発表がされていました。販売に関する情報が広く周知されていない場合、情報戦で消費者は転売業者に負けてしまう可能性があります。ユーザーへの積極的な情報公開は、公平な購入機会の確保の観点からも有効な対策です。
大量増産
任天堂は、スイッチ2について定期的な出荷計画(増産)を行っています。需要と供給のバランスをメーカー側でコントロールすることで、転売業者からの購入を予防することが期待できます。また、このように増産を計画的に行うことは、メーカー側にとって、値崩れのリスクや在庫過多となるリスクの対策にもなる側面があります。
抽選販売の導入
抽選販売については、任天堂独自の対策ではなく、小売店側の対策として行われています。ヤマダデンキ、ビックカメラ、ドン・キホーテ、ゲオ、TSUTAYA、ブックオフ、ノジマなどが抽選販売を導入しています。
応募は1人1回、1商品としている店舗が多く、複数店舗での応募はできるものの、同一店舗で複数回応募したり、同一人物が複数アカウントを作成して応募したりした場合は無効になる可能性があります。その他、小売店のアプリ会員であることを販売資格とするものや、各社条件の厳しさにはばらつきはあるものの、購入ハードルを上げることで転売業者の大量買い占めを抑止しています。
プレイステーション
次に紹介するのは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントから発売されているプレイステーションの転売対策です。
小売店では店頭確認を実施
たとえば、ノジマでは店頭での転売対策を強化しました。店頭において転売目的の可能性のある顧客に対し、購入履歴の提示を求め、再来店時には販売拒否を行い、転売業者に商品が渡らないように対策を行いました。
メーカー側では一定のプレイ時間を購入資格に
「PlayStation®5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」に対し、一定の購入条件を導入することで転売業者と既存のユーザーの差別化を図りました。購入条件の中には「同社が指定したゲーム機を合計30時間以上起動したことがあること。」というものがあり、転売業者が対策を行うことが困難な条件で、画期的な取り組みであるといえます。
転売価格を下げるための対策も
小売店により、転売価格を下げるための対策も行われています。その一つに、商品から新品という価値をはく奪する方法があります。具体的には、商品にあらかじめシールを貼っておき、販売の際にシールをはがし、外箱に傷をつけて開封済みとする方法です。その他、小売店によっては、販売の際に外箱にサインやバツ印をつけて、新品価格をはく奪しています。
ナイキ
最後は、高額転売が問題となったナイキのスニーカーに関する転売対策をご紹介します。
販売規約の変更
まずは、販売規約の変更です。具体的には再販売用購入の禁止について規定しています。再販売用購入の禁止については、ナイキの公式サイトにおいて、最終エンドユーザーに対する直接販売を目的としている旨、再販目的での商品購入を禁止とする旨を明記しています。また、該当する注文を確認した場合には、販売制限、注文取消し、アカウントへの制限等を講じる権利を自社に留保する旨も明記し、転売業者の注文を排除できるようになっています。
ボット対策の強化
ナイキジャパンからの正式な発表はありませんが、アメリカでは2022年10月からボット対策が強化されています。転売ボットとは、不正な自動決済ソフトウェアを指し、アカウントの大量作成、アカウントの乗っ取り、スクレイピング(高速購入)などを行います。主導で購入をしようとする一般消費者はボットに太刀打ちができません。ナイキでは、ボット対策テクノロジーにより、高確率でボットを排除して公平な購入機会の確保に努めています。
- 国民生活安定緊急措置法
-
国民生活安定緊急措置法とは、物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するため、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定め、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保することを目的とする法律です。
現在、米の価格高騰やコメ不足が問題となっていますが、2025年6月13日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が公布され、同月23日より、米穀の転売が規制されることになりました。
従来通り、一般消費者に対して直接販売する小売事業者等が米を最終消費者に販売することは可能ですが、小売事業者等から個人や事業者が、店舗・フリーマーケット・インターネットを通じて不特定多数の者への販売行為を行うことが禁止となりました。ここにいう販売とは、取得価格を超える価格での譲渡を指し、これによって、転売業者が米の転売によって利益を得ることができなくなりました。米穀の転売を行った違反者は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金刑に処せられます。
出典:(農林水産省・消費者庁)「国民生活安定緊急措置法による転売規制についてのQ&A」(https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/tenbai_kisei-7.pdf)
転売対策を行う際の法務面での注意点
転売に対する企業努力や国の対策、転売を取り巻く状況について理解が深まりました。転売対策へのコストを考えると悩んでいたのですが、持続可能なビジネスを行っていくためにも、わが社でも対策を進めていきたいです。法務の観点から注意点はありますか?
はい。転売対策を自社で行う場合には、いくつかの方法や注意点があるので解説していきますね。
転売は特定の法律に違反しない限り、原則として合法
前述しましたが、転売は特定の法律に違反しない限りは合法であるという点に注意する必要があります。一例にはなりますが、特定の法律とは以下を指します。
■無免許で酒類の販売を行った場合には酒税法違反となる(酒税法第56条参照)
■承認や免許なく医療品を販売した場合には薬機法違反となる(薬機法第84条参照)
■偽造チケットの販売、不正な意図でチケットを転売した場合にはチケット不正転売禁止法違反となる(チケット不正転売禁止法第3条参照)
■他人の著作権を含む商品を転売した場合には著作権法違反となる(著作権法第119条参照)
■偽造品、模造品の転売を行った場合には商標法違反となる(商標法第78条参照)
■中古品を許可なく転売した場合には古物営業法違反となる(古物営業法第31条参照)
契約自由の原則により、メーカー側も転売業者に対して売らない権利があるといえますが、転売事業者に売らない(NO)を突き付けるよりも、事前に転売を困難にする仕組み、転売事業者が仕入れを尻込みする仕組みを作ることが重要です。
商標権の活用
転売対策を行うための法律上の根拠として、商標権の活用が可能か、考えてみましょう。
商品の転売は、原則として商標権の侵害にはあたりません。一度市場に流通した商品(真正商品)については、その商品に付された商標権の効力は目的を達成し、使い尽くされた(消尽した)と解釈されるためです(商標権の消尽)。
しかし、全ての転売が合法というわけではありません。転売の態様によっては、商標が持つ重要な機能である「出所表示機能」や「品質保証機能」を損なうと判断され、商標権の侵害にあたる場合があります。たとえば、商品を小分けにして転売・改変して転売するケースです。実際に、たとえば、メーカーが販売している健康食品・サプリメントを、小分けにしてECモールで出品しているような業者が存在します。このような行為は、メーカーが保管状態や品質管理が維持されず、元の商品と同じ品質であるとはいえないため、商標権の侵害(品質保証機能が害されたこと)を主張して販売の差し止めを求めることが可能です。
・他者と同じ商標を使用できる場合とは?|商標的使用について弁護士が解説
利用規約・販売規約への明記
ECで自社製品を販売している場合には、ECサイトの利用規約や販売規約に転売を禁止する旨を記載することも、転売対策の1つです。転売業者がサイトから商品を購入する場合には、転売を禁止する文言を盛り込んだ利用規約に同意することになりますので、転売を行った場合には規約違反を根拠として、転売行為の中止を求めることが可能です。
また、転売禁止とは別に、規約違反のペナルティとして会員資格のはく奪、サイトの利用停止を行うことができる旨を明記しておくことも方法の1つです。また、規約違反により会社に損害が生じた場合には、その損害を幅広く請求する可能性があるといった文言を組み込むことも、転売業者にとって心理的なプレッシャーがかかり、抑止力になります。
商品へシリアル番号を導入
転売が行われてしまった場合に備えて、商品にシリアル番号を導入することも効果的です。シリアル番号とは、1つ1つの製品に連続して付与された固有の番号を指します。この番号によって、1つ1つの製品を特定することができます。類似する番号にロット番号というものがありますが、ロット番号は、同材料・同工場・同タイミングで作られた一定数の製品に付与される番号です。こちらは、同一番号によって品質が担保されるメリットがあるものの、シリアル番号のように個別の製品を特定することはできません。
シリアル番号の付与を行い、出荷情報とシリアル番号を一覧にしてきちんと紐づけることにより、転売が行われた場合にはシリアル番号を通じて、転売者の追跡と特定が可能になります。そのうえで、特定された購入者への販売を停止することで、転売ルートを止めることが可能になります。また、シリアル番号を厳格に管理しているという体制自体が、転売業者への抑止力となることが期待できます。
転売対策に法的な拘束力はあるか?
メーカー側が転売を禁止した場合、どこまで転売業者を法的に拘束できるのでしょうか。いくつかのパターンに分けて考えてみましょう。
「転売目的の購入禁止」を明記したパターン
転売を禁止するのではなく、転売を目的とする購入を禁止にするパターンです。この場合には、購入後に転売が行われたとしても、転売目的であったことを証明できないと、規約違反の責任を追及できなくなる可能性があります。
転売を業とする者によって購入されていること、実際に転売を行っていることなどから、転売目的での購入であったことを証明していくことになります。もっとも、転売業者から「プライベート用で購入した。」「個人的に購入したが不要になったので転売をした。」等の反論は想定されますので、証拠の準備を入念に行うことが重要です。
転売禁止特約を付したパターン
民法では契約自由の原則から、契約の当事者間で自由に契約内容を定めることを認めていますので、売買契約(利用規約・販売規約)の中に付した転売を禁止する特約は有効です。
このような、契約違反を根拠として、転売行為の中止を求めることは、法律的にも筋が通っています。マーカーからの購入者が転売業者である場合には、有効な対策になり得ます。
転売業者から購入した第三者との関係
企業側が定めた転売を禁止する特約は、転売業者から商品を購入した第三者に対しても主張できるのでしょうか。民法には債権の相対性という原則があります(民法第440条参照)。転売禁止特約は売買契約の一部であり、特約の効力はあくまでも契約の当事者間にのみ及びます。
そのため、転売禁止特約違反があった場合に、メーカー企業側は自社からの購入者に対しては契約違反を主張できるものの、自社の購入者から商品を購入した第三者に対しては、転売禁止特約を主張して商品の返却等を求めることは、原則としてできません。転売商品を出品している業者から、「卸売業者から仕入れているので、貴社の利用規約には拘束されない」と反論される可能性があります。
このような場合は、法律事務所に支援を求めましょう。
転売対策のお悩み、リスク、課題は解決できます
先生、今日はありがとうございました。転売対策について理解が深まりました。前向きに転売対策を行いたいのですが、慎重に進めたいのでアドバイスをもらえますか?
もちろん可能です。貴社の転売被害の現状をよくヒアリングし、最も有効となる対策を一緒に考えます。既存のユーザーの購買意欲を低下させないためのビジネス上のアドバイスも可能です。転売対策を成功させ、貴社のビジネスをさらに飛躍させましょう!
この記事では、ECサイトの運営を行う企業の皆さまが、転売対策を考えている場合に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスや商品に対する、顧客や社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、EC事業における転売対策についての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「どこから始めるか悩んでしまいがちな転売対策について、無駄なくスムーズに進めることができる。」
「転売業者への様々なアプローチを通して、不当な値段で自社商品が転売されることを防止できる。」
「転売対策について社の取り組みとしてアピールすることにより、消費者からの好感度が上がり、サイトの評価も向上する。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「自社がかけられるコストやリソースに応じた適切な転売対策を提案してもらえた。」
「法的アドバイスはもちろん、EC専門家としてのビジネス的なアドバイス、システム導入についてのアドバイスをもらい、EC事業自体の発展にもつながった。」
「転売に対してどのような対応を取るのか、業務フローの作成やコンプライアンス研修も任せられ、社内の意識やオリジナル商品への愛着、従業員の対応力が向上した。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の記載内容は、2025年7月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。