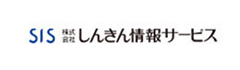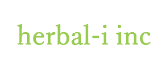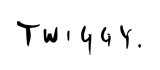商標権侵害VS真正品がわかる:EC事業者が知っておくべき商標権のルールと安全な商品販売のチェックポイントを徹底解説!
通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを運営する企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「ECサイトでブランド物の真正品の販売を行いたいが、法律上の問題はないだろうか。」
「ECサイトにて海外ブランド品の取扱いを考えているが、正規輸入と並行輸入では何が違うのだろう。」
「他社の商標を含む商品を輸入し、販売する際に気を付けるべき点を知りたい。」
この記事では、EC事業者が、ブランド物の真正品を販売する際に知っておきたい商標法上のルールや注意点についてEC専門の弁護士が詳しく解説します。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
目次
商標権侵害とは?基本的なルールと注意点
当社はECサイトにて化粧品や香水の販売を行っています。この度、若者に人気の海外ブランドの化粧品を輸入し、サイト内にて販売することを検討しています。仕入れについては、日本の代理店から購入するよりも、海外の製造者または輸出者から購入する方が安価であるため、並行輸入を行うことを考えています。どのような点に注意し、ビジネスを進めていけばよいか、アドバイスを頂きたいです。
なるほど。今日は真正品を販売する際の商標法上のルールについてですね。
商標権とは、商品やサービスに付された商標を保護し、商標権者の権益を守るための権利です。商標には商品やサービスの出所を識別する①出所表示機能、その品質を保証する②品質保証機能、その商品やサービスの購買意欲を喚起させる③広告宣伝機能があり、これらを商標の三大機能といいます。特に、①出所表示機能、②品質保証機能は重要であるため、真正品の販売においても、商標や商品の状態について注意することが重要です。
まずは、商標の定義と注意点について解説します。
商標権の定義とその保護対象
事業者が、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するマークのことを商標といい、商標を独占的に使用する権利のことを商標権といいます。商標には、文字・図形・記号・立体的形状・これらを組み合わせたものなど、様々なタイプがあります。また、平成27年4月から、動き商標・ホログラム商標・色彩のみからなる商標・音商標・位置商標について商標登録が可能となりました。
商標制度の趣旨目的は以下の通りです。
(商標法第1条)
「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」
前述した通り、商標の3大機能を守ることが、商標を信じて購入した消費者の利益の保護や、商標を会社の顔として使用している企業の信頼の保護といった、商標法の趣旨目的につながると分かります。
後述しますが、商標と商標が付された商品・サービスは基本的にセットで考えるため、商標権の侵害の判断をする際には、①商品・サービスが同一または類似であるかどうか、②商標が同一であるかどうか、の2点が重要な判断材料になる点にもご留意ください。
商標権侵害の具体例と判断基準
商標権侵害の具体的な例として、第三者が商標権者の許諾を受けずに同一または類似の商標を、当該商標が付された商品(指定商品)やサービス(指定役務)と同一または類似の商品やサービスに使用する場合が挙げられます。
たとえば、人気のブランドバッグに似たロゴを使用したバッグを販売した場合は、商標権侵害が成立する可能性があります。侵害が成立するかどうかの判断基準は、消費者がその商標を見た際に、商標権者の商品と誤認・混同する可能性があるか(出所表示機能が損なわれたか)どうかも判断ポイントの1つとなります。
品質保証機能と出所表示機能の関係性
前述した通り、商標には品質保証機能、出所表示機能、広告宣伝機能といった3つの重要な機能があります。ここでは、3大機能のうちの品質保証機能と出所表示機能の2つにフォーカスします。品質保証機能とは、その商標が付された商品やサービスが一定の品質を保っていることを消費者に示す役割です。消費者は、同じ商標を見れば、その商標を見ただけで、その商品やサービスがどのような品質であるか理解することができます。
出所表示機能は、その商標が付されている商品やサービスは、いつも同じ出所から出ていることを示す役割があります。たとえば、スーパーのプライベートブランドの商標の場合、その商標を見れば、「これは〇〇ストアの商品だ。」と消費者は理解できます。これが出所表示機能です。これらの機能が損なわれる場合、商標権侵害が成立する可能性もあります。
違法になるケースと違法でないケース
商標法における商標権の基本的な侵害要件は前述した通りですが、実務上は、他人の商品・役務・商標と同一または類似の商標を単に使用しただけでは、商標権の侵害は成立しないとされています。具体的には、商標的使用という考え方が重要で、前述した商標の三大機能を実質的に損なっていないかどうかで判断します。商標権者は、自社の商標が使用されていれば、商標権の侵害に該当するかどうかにかかわらず、警告文を送ってくることもあります。具体的な侵害の有無に関連する事項ついては、弁護士や弁理士といった専門家に相談をし、冷静に判断を行うことが重要です。
・他者と同じ商標を使用できる場合とは?|商標的使用について弁護士が解説
真正品の販売における商標権の考え方
他社の商標を使用したからといって、必ずしも商標権の侵害になるわけではないんですね。少し理解が深まりました。
それはよかったです。次に、真正品の販売にあたって、 “真正品” “正規品” “並行輸入品” についての基礎知識と、商標法上の考え方について解説していきます。
真正品とは?その定義と判断基準
真正品、正規品、並行輸入品の用語については下記の通りです。
■真正品
真正品とは、商標権を有する権利者によって適法に販売された商品を指します。あくまで適法なルートであるかどうかが問題となるため、真正品には正規品や並行輸入品も含まれる場合があります。また、真正品であっても、流通する過程で改造が加えられた商品に元の商標を付している場合や、小分けにした商品にわざわざ再度元の商標を付した場合には、それらの行為が商標権の侵害と認められる可能性があります。(東京地裁平成4年5月27日判決)(大阪地裁平成6年2月24日判決)
■正規品
海外ブランドから正式に認められた日本の正規代理店が、メーカーから直接輸入し、正規の代理店にて正規の価格で販売される商品を指します。正規の代理店以外にも、外国の直営店やブランドショップで購入した商品についても正規品といえます。
■並行輸入品
正規代理店とは異なるルートで輸入した商品のことを指します。たとえば、並行輸入品販売店のバイヤーが、海外の正規代理店や免税店で仕入れた商品を日本で販売するケースが該当します。この場合には、日本の正規代理店や直営店は経由しないこととなります。
商標権の消尽と販売の正当性
商標権には「消尽」という知的財産全般に及ぶ原則が適用されます。消尽とは、商標権者またはその許諾を得た者が一度権利を行使した(市場に流通させた)場合、その商品の販売に関する商標権が消滅し、商標権者がその後の販売に干渉できなくなるというものです。この原則に基づき、商標権者自身やその許諾を受けた者が正当に流通させた商品を第三者が再度販売する行為は、商標権侵害には当たりません。たとえば、商標権者が販売した商品を小売業者がそのまま販売したり、消費者が中古市場で転売したりする場合は正当な行為とされます。
並行輸入品の取り扱いとそのリスク
並行輸入品は、正規代理店以外の経路を通じて輸入された真正品を指します。これが合法であるためには、商品が商標権者の承諾を得て製造されていることや、当該商標の品質保証機能・出所表示機能が損なわれていないことが条件です。しかし、並行輸入品にはいくつかのリスクが伴います。たとえば、製品説明書が現地言語で用意されていない場合や、輸入時に法令違反がある場合、問題となることがあります。そのため、並行輸入品の販売には、慎重な確認と適切な手続きが求められます。
再包装・再販売に伴う法的注意事項
商品を再包装したり、付属品を変更したりする場合には、商標法上の問題が生じる可能性があります。再包装や付属品の変更、商標が付された商品の加工や改変が加えられた場合、商品の品質や商標に対する消費者の信頼が損なわれる場合もあり、それが商標権侵害と判断されるケースもあります。商標法における品質保証機能や出所表示機能が重要な要素として扱われるため、商品の再販売などを行う際には、これらの機能に影響を及ぼさないよう注意が必要です。安全に再販売を行うためには、元の商品状態を維持し、消費者に正確な情報を提供することが求められます。
- 非典型的な商標権の侵害行為と事例
-
商標権の侵害行為は、典型的な商標権侵害行為と、非典型的な商標権侵害行為の2つに分けることができます。典型的な商標権侵害行為とは、他者の商標と同一または類似の商標を、当該商標が付された商品・サービスと同一または類似の商品・サービスに使用することで、1-2「商標権侵害の具体例と判断基準」でも詳しく解説しています。
一方で、非典型的な商標権侵害行為とは、具体的に下記のようなものが挙げられます。
■真正商品であっても、それを小分けにしたり、改変、加工する形で再販を行うこと
■真正商品に付された商標をはく奪して販売すること
■真正商品を再包装して、かつ商標を付して販売すること
■商標権者が廃棄を予定していたにもかかわらず、その商品を勝手に販売すること他者の商標を商標的使用するだけでなく、真正商品を販売する場面においても、非典型的な商標権侵害行為として抵触する可能性がありますので注意が必要です。次に、非典型的な商標権侵害行為の判例をご紹介します。
■HERSHEY’S事件(福岡高裁昭和41年3月4日判決)
大袋入り業務用ココアを小分けし、当該ココアの登録商標と同一の商標を付して再度包装をし販売した事例です。商品の性質上、再包装によって品質の変化・異物混入が考えられる点から、当該行為は商標権者の信用を毀損し、購入者の不利益となるという理由で、裁判所は商標権の侵害を認めました。■Nintendo事件(東京地裁平成4年5月27日判決)
従前の商標を付したまま、ゲーム機の本体とコントローラーを改変した商品を販売していた事例です。登録商標はそのままに改変した商品を販売する行為は、改変後の商品を商標権者が販売していると需要者に誤解を与える可能性がある点、改変後の商品の品質について品質表示機能が害される可能性がある点を考慮して、商標権の侵害を認めました。■ハイミー事件(最高裁昭和46年7月20日決定)
パチンコ業者に対し、景品用として一度卸売りされた調味料を、被告がパチンコ業者から買い集めて新しい段ボール箱に包装し、あたかも新品であると装い、再度パチンコ業者に卸売りしようとした事例です。本事例では、不正の利益を得ることを目的としたという特別の事情も加味され、商標権の侵害が認められました。真正商品であっても、販売の方法や態様によっては非典型的な商標権侵害行為に該当する可能性があります。真正商品の販売にあたっては、弁護士や弁理士といった法律専門家に相談をしながらビジネスを進めていくことをお勧めします。
模倣品・横流し品との違いと注意したい点
商品が本物(真正品である)というだけで安心してはだめで、その商品の販売の仕方にも気をつけないといけないんですね。そういえば、並行輸入品、横流し品、模倣品などの判断が難しいと感じているのですが、これらの違いや注意点を教えていただけますか?
適法な商品を正しい形で販売することが重要です。それでは、それぞれの違いや考え方について解説していきますね。模倣品は誤って取扱ってしまうと会社の信用問題にもかかわります。商品を仕入れる際には、仕入れ業者の選定や契約内容について精査し、できる限り模倣品のリスクを低減されることをお勧めします。
横流し品・模倣品・並行輸入品の違い
正規の商品を模倣して製造・販売された商品を模倣品といいます。これらは、商標法が保護する登録商標を無断で使用している場合が多く、商標権侵害となることが一般的です。たとえば、有名ブランドの商品名やロゴをそのまま使用して製造された偽バッグやアクセサリーは典型的な模倣品です。このような模倣品は、消費者に商品の出所を誤認させてしまい、商標の信頼性を損なう危険性が高いため、厳しく規制されています。
横流し品とは、本来は特定の流通ルートで販売されるべき商品が、意図しない第三者を通じて市場に流れるケースを指します。たとえば、メーカーが正規代理店のみに供給するはずだった商品が、代理店から無許可で他の販売業者に流れる行為が該当します。多くの場合、横流し品は真正品であるケースが多いですが、その流通経路が問題視されることがあります。特に商標権者の承諾を得ていない場合、商標権侵害が成立する可能性があります。
ここでは、模倣品・横流し品・並行輸入品の違いについて一覧にしました。ご参照ください。
| 模倣品 | 横流し品 | 並行輸入品 | |
| 商品の真正 | 偽商品 | 原則 真正品 | 真正品 |
| 流通ルート | 製造事業者から流通業者・小売店・見本市など | 特定の流通ルートから意図せず外れる形
|
正規代理店とは異なる
(海外ブランド→海外直営店・免税店など→並行輸入業者→消費者) |
| 商標権者の許諾 | なし | 原則 なし | あり |
| 商標権侵害の可能性 | 原則としてあり | 商標権者の許諾がない場合には、問題となる | 原則としてなし
(小分け・改変・加工などをした場合にはあり) |
模倣品販売による法的リスク
模倣品の販売を行った場合には、一例ですが以下のようなリスクが想定されます。
■商標権者から模倣品の販売の差止請求を受ける(商標法第36条)
■商標権者から模倣品を扱っているECサイトの停止を求められる(商標法第36条)
■模倣品の販売によって得た利益相当額の損害賠償請求を受ける(商標法第38条)
■10年以下の拘禁刑もしくは1千万以下の罰金またはその両方の刑罰を受ける(商標法第78条)
■模倣品を取り扱ったことにより悪評が拡散し、消費者からの信頼を失う
真正品販売に潜む模倣品のリスク
真正品であっても、模倣品が混在する可能性には注意が必要です。たとえば、並行輸入品として購入された商品が、正規の製造業者の手を経ていない模倣品であれば、商標法との関係で商標権の侵害とみなされる可能性があります。また、真正品と模倣品の区別が付きにくい状況で販売すると、消費者とのトラブルにつながることがあります。このため、販売者は商品を仕入れる際に厳密な確認をし、模倣品が含まれていないか注意を払うことが重要です。
商標権侵害対策と安全な商品販売方法
仕入れについては、仕入れ業者から並行輸入品を仕入れようと考えているのですが、仕入れ業者の選定を社内で厳正に行ったり、契約書を締結したりして、きちんとした品を仕入れられるようにしたいと思います。最後に、本日のお話を踏まえて、リスクを低減しながら、安全に真正品の販売を行えるような注意点を教えていただけますか?
もちろんです。次に安全な販売についての基本ルールと注意点を解説していきます。
商品を安全に販売するための基本ルール
商品を安全に販売するためには、商標権の基礎知識を理解し、商標法違反を避けることが重要です。具体的には、販売する商品の商標が適切に登録されているか、その商標の使用が商標権者の権利を侵害しないかを確認する必要があります。真正品の場合でも、商品の改造やラベルの変更がされていないか注意が求められます。また、商標が持つ出所表示機能を損なわない形で販売することが大切です。これらの点を把握しておくことで、販売者として商標権侵害のリスクを回避できます。社内でコンプライアンス研修を行い、商標権をはじめとした知的財産権についての意識を高めることも方法の1つでしょう。
並行輸入や再販売の手続きと注意点
並行輸入や再販売を行う際には、その流通プロセスが商標法に違反しないか、慎重に確認する必要があります。並行輸入品は主に正規代理店以外のルートで輸入された真正品ですが、この場合でも商標を付した商品が商標権者の許諾を得た形で流通していることが基本条件です。この「商標権の消尽」という考え方に基づき、商標権者が一度販売をし、権利を行使した場合には商標権侵害とはならないとされています。しかし、流通過程で商品の改造や誤解を招くような変更が行われた場合、商標権を侵害する危険性があります。したがって、商標権者の許諾の有無、商標権者の権利行使の有無、商品が元の状態で適正に流通していることなどを確かめることが重要なポイントです。
販売者が行うべき真正品の確認方法
販売者として確認すべきこととして商品が真正であるかどうかという点があります。その確認方法としては、商品の購入ルートが正規であるかどうかについての文書や契約書類を確認すること、商品のシリアル番号や識別コードを正規のデータベースで照合することなどが挙げられます。また、商品の品質や包装状態にも注意することで、模倣品や横流し品を識別する助けとなります。商標権侵害に該当する商品を誤って販売してしまわないように確認作業を徹底し、社内にて確認フローを構築し、慎重な対応をすることが必要です。
真正品販売のお悩み、リスク、課題は解決できます
今日はありがとうございました。新しいビジネスを開始するにあたり、事前に相談ができて大変助かりました。真正品の販売について各種契約書のチェックや、模倣品排除のためのコンプライアンス研修、確認フローの構築などやることが山積みですが、これらについて包括的にご相談することは可能でしょうか?
もちろん可能です。新たなビジネスにおけるリスクの洗い出しはもちろん、それに伴う社内のコンプライアンス研修、契約書のリーガルチェックなども行うことができます。もちろん、トラブル発生時の迅速な対応についてもお任せください。
この記事では、ECサイトの運営を行う企業の皆さまが、ECサイトにて真正品の販売を行う場合に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、EC事業における真正品の販売を含む、商標権の問題についての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「真正品の販売を行うにあたって、リスクを適切に洗い出し、安心して事業を進めることが可能になる。」
「真正品の取扱いの際の、確認フローの構築、社内コンプライアンス研修など、専門家に相談をしながら進めることができる。」
「商標権者からの警告書やECプラットフォームによる規制についても、慎重かつ迅速な対応を行うことができる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「新しい商品を取り扱うことに不安はあったが、起こりうるリスクを丁寧に説明してもらい、ECサイト内の商品ページのチェックもしてもらい、安心して販売をスタートできました。」
「社内に法的知識のある人材がいないことが懸念点であったが、定期的なコンプライアンス研修や法令改正のお知らせをいただき、分からないことはチャットで素早く相談できるため、社内のコンプライアンス意識が向上したと感じる。」
「あるとき、当社で取扱いのある商品の商標権者を名乗る会社から警告文が送付されたが、きちんと調査と対応をしていただき、結果としてその商品の販売を継続することができました。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の記載内容は、2025年6月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。