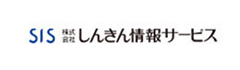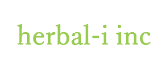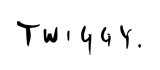通販サイトやオンラインモールなどでEC事業を運営されている企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「ECで販売している自社のオリジナル商品が模倣され、市場に出回っている!どうしたらよい?」
「オリジナリティあふれる画期的な新製品を開発できた!他社に真似されることなく、最大限に利益を出すには?」
「ECサイトの自社製品について、第三者から権利侵害していると言われてしまったら?」
「特許権以外に、利用できそうな知的財産権はあるのだろうか?意匠権や実用新案権って何だろう?」
「自社で新しい商品のデザインを開発したが、デザインが模倣されないためにはどうすればよいのか?」
この記事では、EC運営において大切な権利である “知的財産権”(なかでもビジネスに関連する5つの権利:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権)について、それぞれの違いを整理し、さらには侵害を受けた場合の対応方法まで、ECと知的財産権に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
目次
知的財産権とは?知的財産権の定義とその重要性
EC運営を行う上で、オリジナル商品や新しいサービスを提供したにも関わらず、他社に簡単に模倣されてしまうことは大きなリスクです。自社の成果を守り、発展させるためには知的財産権という法的権利を理解し、活用することが重要です。
著作権、特許権、商標権などは、それぞれ管轄機関(文化庁、特許庁等)が保護を行っています。なかでも、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つは、特に産業と深いかかわりを持つものとして産業財産権と呼ばれ、特許庁に出願し、審査等の所定の手続きを経ることで登録が可能となり、権利として保護されることとなります。しかし、産業財産権を活用していない場合でも、他者から権利侵害の警告を受けるなど、予期しないトラブルに巻き込まれることもあります。EC運営を行う企業にとって、知的財産権の基本を理解しておくことは、リスク管理の一環として非常に重要です。
知的財産権とは
知的財産権とは、人間の知的創造活動の成果を一定期間、独占的に保護するための法的権利です。この権利は、特許権や実用新案権、意匠権、商標権、著作権などによって構成されています。これらの権利は、技術革新や創作活動を奨励し、産業の発展を促進する役割を果たします。特に産業財産権として知られている権利群は、産業界における知的財産の保護を目的としています。
■知的財産権の種類
ア)知的創造物についての権利等
・特許権(特許法)※
・実用新案権(実用新案法)※
・意匠権(意匠法)※
・著作権(著作権法)
・回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
・育成者権(種苗法)
・営業秘密(不正競争防止法)
イ)営業上の標識についての権利等
・商標権(商標法)※
・照合(商法)
・商品等表示(不正競争防止法)
・地理的/物理的表示~GI
※産業財産権(特許庁所管):特許権、実用新案権、意匠権、商標権
出典:「知的財産権について」(特許庁)より一部加工の上引用(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html)
知的財産権の重要性
知的財産権は、新しい技術や製品の革新の基盤となり、産業発展を支える重要な役割を果たします。例えば、特許権は発明を保護し、その技術を他者が無断で利用することを防止します。また、意匠権や商標権は、商品のデザインやブランドイメージを守り、市場での競争力を保つための手段となります。これにより、企業や創作者は自身の開発した技術や作品を安全に展開し、さらなる創造活動を進めることができるのです。したがって、知的財産権の適切な取得と活用は、企業の競争力維持や経済成長において欠かせない要素となっています。
知的財産権~ECビジネスに関連する5つの種類
①特許権
特許権は、技術的な発明を保護するための権利です。特許出願から20年間、発明者に対して独占的な実施権が与えられます。これにより、他者が許可なく同様の技術を製造、使用、販売することを防ぐことができます。特許権は、特に革新的な技術や製品を生み出す企業や個人にとって重要な知的財産権です。
②実用新案権
実用新案権は、物の形状や構造に関する考案を保護します。特許権と比較して、より簡易かつ短期間での取得が可能です。特許権が技術的な詳細を重視するのに対し、実用新案権は実用的な改良に対して権利を提供します。このため、特許権と実用新案権の違いを理解することで、最適な選択が可能となります。
③意匠権
意匠権は、製品のデザインや形状、模様、色彩などを保護する権利です。製品の美的外観が重要となる業界において特に有用です。この権利を得ることで、独自のデザインを模倣されることを防ぎ、ビジネスにおける競争優位を保つことができます。意匠権の存続期間は出願から25年間です。
④商標権
商標権は、商品やサービスに使用されるマーク(例えばロゴやブランド名)を保護する権利です。商標は、消費者に対する識別資産として機能し、ブランド価値を高めます。商標権を取得することで、無断使用を防ぎ、ブランドの安全を確保することができます。この権利は登録から10年有効で、期限を過ぎても更新が可能です。
⑤著作権
著作権は、文学、音楽、映画などの創作物を保護する権利です。著作権は創作と同時に発生し、登録の必要はありません。この権利により、著作者は作品の利用に関する排他的権利を持つことになります。著作権の保護期間は通常著作者の死後70年です。創作活動を支えるために欠かせない権利と言えるでしょう。
権利の違いと具体的な使い分け
技術的なアイデアを保護する特許権
特許権は、新しい技術や発明を独占的に保護するための権利です。この権利によって、新しい技術的なアイデアや発明を模倣から守り、発明者がその成果を活用することができます。例えば、通信技術や製造方法に関する新しい発明などが特許権で保護されます。
特許権を得るためには、まず特許庁に特許出願をして、審査を経て特許査定を受ける必要がありますが、審査で特許が認められる、つまり特許の要件としては、発明が新規性、進歩性、産業上の利用可能性を満たす必要があります。嚙み砕いて言うと、特許権は技術革新を保護するため、発明が新しいアイデアであり、業界の技術進歩に寄与することが求められるということです。
実用新案権と特許権の違い
実用新案権も技術的な考案を保護しますが、特許権との違いは以下の通りです。
・実用新案権は物品の形状や構造に関するアイデアを保護します。
・特許権は新しい技術や発明に焦点を当てており、より詳細な審査が求められます。
・実用新案権は審査なしで簡素な手続きで登録可能で、比較的短期間で取得できます(最大10年の保護)。
実用新案権は、例えば、改良型ベルトのデザインなどが対象となります。
デザインを保護する意匠権
意匠権は、製品のデザインを保護するための権利で、形状や模様、色彩などが対象です。例えば、家電製品や車両などのデザインが意匠権によって保護され、他社によるデザインの模倣を防ぐことができます。
意匠権は最大25年間の保護が受けられます。
ブランドを守る商標権
商標権は、商品やサービスを他社のものと区別するためのネーミング、ロゴ、マークなどの目印(=商標)を保護する権利です。もし、自社の商標を勝手に他人に使われてしまったら、せっかく築いたブランドイメージが崩れたり、売上を奪われたりするなど損害が生じるリスクがあります。商標権を登録し保護することで、こうした事態を防ぎ、自社の利益を守ることにつながります。
商標権は登録から10年間存続しますが、何度でも可能な更新手続きにより、永続的に存続させることができます。そのため、長期的にブランド価値を維持するために重要な手段となっています。
創作物に対する著作権
著作権は、文学や音楽、芸術作品などの創作物を保護するための権利です。この権利により、著作者はその作品の使用をコントロールし、経済的利益を得ることができます。著作権は創作と同時に自動的に発生し、特別な手続きなしに保護が受けられます。作品が公開された後であっても著作権は維持され、他者による無断使用や模倣を防止することが可能です。このように、著作権は幅広く創作活動を支える重要な要素となっています。
・ECサイト・ウェブサイト・ホームページの著作権を知ろう!専門の弁護士が注意点を解説
知的財産権の申請と維持管理
権利取得のプロセス
知的財産権の取得は、発明や創作物を法的に保護するための重要なステップです。本記事で解説している権利のうち、著作権以外の権利(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)は、権利取得のためにはまず出願が必要です。以下に、5つの権利の取得プロセスを簡潔にご紹介します。
①特許権(技術的な発明を保護)
・手続き:必要(審査あり)
・取得方法:特許庁へ出願 → 審査請求 → 審査通過後に登録料納付 → 登録
・ポイント:発明としての新規性・進歩性が求められる。審査が厳格。
発明の内容を詳しく記載した特許明細書を作成し、特許庁に提出します。このプロセスは審査を含み、出願から登録まで約2〜5年を要することがあります。
②実用新案権(比較的簡易な技術的アイデア)
・手続き:必要(審査なし)
・取得方法:特許庁へ出願(出願時に出願料と併せて3年分の登録料も一括納付)→ 方式審査のみで登録
・ポイント:早期に権利化できるが、後に無効となるリスクも。登録後に技術評価書の請求が必要な場面も。
実用新案権は、審査なしで簡易な手続きで取得でき、出願から登録まで約3ヶ月かかります。
③意匠権(物の形状やデザインを保護)
手続き:必要(審査あり)
取得方法:特許庁へ出願 → 審査通過後に登録料納付 → 登録
ポイント:美的なデザインであること、創作性があることが求められる。
意匠権の場合、新しいデザインを保護するための出願を行い、約6ヶ月で登録が完了します。
④商標権(商品名やロゴなどブランドを保護)
手続き:必要(審査あり)
取得方法:特許庁へ出願 → 審査通過後に登録料納付 → 登録
ポイント:識別力があること、他者と紛らわしくないことが必要。更新可能(10年ごと)。
商標権はブランドの識別を目的としており、登録後10年ごとに更新が可能です。
⑤著作権(文章、音楽、写真などの創作物)
・手続き:不要(創作と同時に自動発生)
・取得方法:原則として手続き不要。登録制度はあるが任意。
・ポイント:創作した時点で自動的に権利が発生。登録すると訴訟などで有利になる場合もある。
- 商標登録のNG例とその理由
-
せっかく出願しても、商標登録が認められないケースは意外と多くあります。
特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査していますが、特許庁のウェブサイトには、登録が認められない商標として、以下の1~3が挙げられています。1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの今回は、特に1.について、主なポイント(①~③)を、例を挙げながら詳しくみてみましょう。
1.自己と他人の商品・役務を区別することができないもの(商標法第3条)
商標は、自己と他人の商品又は役務とを区別するために用いられるものであるため、以下に該当する商標は登録が認められません。①商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)
商品又は役務の「普通名称」を「普通に用いられる方法」で表示しているだけの商標は、認められません。
「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、略称や俗称も普通名称として扱います。また、「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。
(例)商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」または「アルミ」を出願した場合
(例)商品「パーソナルコンピューター」に使用する商標として「パーソナルコンピューター」または「パソコン」を出願した場合②商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)
「慣用されている商標」とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。
(例)商品「清酒」に使用する商標として「正宗」を出願した場合
(例)役務「宿泊施設の提供」に使用する商標として「観光ホテル」を出願した場合③単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)
商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
(例)商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合出典:「出願しても登録にならない商標」(特許庁)(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html)を一部加工、追記のうえ引用
さて、①の「普通名称」と、③の単なる「商品の品質」を組み合わせた商標として、「おいしい牛乳」が思い浮かぶ方もおられるかもしれません。
「おいしい牛乳」は、商品の品質である「おいしい」と、普通名称「牛乳」を組み合わせただけですので、「識別力」が無く、実は商標として認められていません。商標として認められ、登録されているのは、「明治 おいしい牛乳」(商標登録第5490410号)や「森永のおいしい牛乳」(商標登録第5109129号)などになります。これらは、社名が入っていることなどから、「識別力」が認められ、商標として登録されています。
ブランドの顔ともいえる商標ですので、NG例を知り、J-Platpatなどで既存の登録をチェックのうえ、オリジナリティのあるネーミングを心掛けることで、スムーズな出願、登録につなげていきましょう。また、戦略的にどうしても説明的な名前にしたいときなどは特に、知的財産権に詳しい弁護士などの専門家に相談することも方法のひとつです。
・他者と同じ商標を使用できる場合とは?|商標的使用について弁護士が解説
権利の維持と管理方法
取得後の知的財産権を維持するためには、定期的な手続きと費用が必要です。特許権は、毎年設定された特許料を納付し続けることで、最大20年間の保護が得られます。意匠権も同様に、権利が有効であるためには所定の意匠登録料が必要で、この権利は最長25年間維持できます。商標権は10年ごとに更新手続きが必要であり、更新を怠ると権利が失効する可能性があります。
さらに、知的財産権を有効に活用するためには、自社の権利が侵害されていないか、定期的に調査を行い、もし権利侵害があった場合には早期に適切な対応を取ることが重要です。知的財産権の違いを理解し適切に管理することで、企業の技術やブランド価値をしっかりと守ることができます。
知的財産権の侵害とその対策、侵害を受けた場合の対応
まず、自身が所有する著作権や意匠権、商標権、特許権、または実用新案権が本当に侵害されているかを確認する必要があります。専門家の助けを借りて、具体的な侵害内容を特定し、証拠を集めましょう。
その後、侵害者との交渉を開始する前に、知的財産権に詳しい弁護士と相談して、法的措置を含む適切な対応策を検討します。多くの場合、最初に侵害者に対して侵害の通知を送付し、問題解決に向けた交渉を試みます。この段階で解決できない場合は、裁判所の差止命令を求めるなど法的行動に移行することも考えられます。
知的財産権の侵害対策を考えるためには、成功した事例から学ぶことが有用です。例えば、ある企業が自社の商標が無断使用されていることを発見した場合、すぐに侵害者に差し止め通知を送り、交渉により解決した例があります。また、特許権が侵害された場合においては、裁判所を通じて差止めを行い、損害賠償を取得したケースもあります。
こうした事例から、知的財産権を事前にしっかりと管理し、ホームページなどを活用して、自社の権利を広く周知することも、無用な侵害を未然に防ぐ手段となります。また、実際にトラブルになったときに慌てることのないよう、平素から知的財産権に詳しい弁護士と連携を取り、アドバイスを得ながら自社の知的財産権の管理を行っていくことも有効な対策といえるでしょう。
最後にこれら対策のポイントをまとめておきます。
■知的財産権の侵害を受けた場合の対応例
・具体的な侵害内容を特定し、証拠を集める
・侵害の通知を送付
・交渉
・裁判所の差止命令
・損害賠償請求
■自社の知的財産を守るため、または実際に侵害を受けた場合迅速に対処するための対策例
・知的財産権の登録
・知的財産権の管理
・自社の権利を広く周知
・弁護士等専門家との連携
ECの知的財産権についてのお悩み、リスク、課題は、解決できます
この記事では、EC事業の運営を行う企業の皆さまが、自社の知的財産を守るために、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、EC事業における、特許権や意匠権、著作権といった知的財産権に関する問題など、専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「企業の利益を守るために大切な“知的財産権”について、ビジネスに則した実践的なアドバイスをもらいながら、登録などの必要な手続きを進められる。」
「“知的財産権”に関する法改定や新しいガイドラインについて、最新の情報に基づいたアドバイスを受けることができる。」
「他社に商品を模倣されるなどして損害を被るリスクを最小限に抑えながら、積極的にECビジネスを進めていける。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「自社の商品やブランドイメージを守るために、どの知的財産権を利用すれば良いのか、さらに具体的にどのような手続きを取ればいいのか教えてもらえて助かった。」
「専門家としてのアドバイスを適宜得ることができたので、スピード感を持ちつつ、知的財産権を守りながらビジネスを進めることができた。」
「自社の知的財産権が侵害された場合にどのように対処したらよいか、実際に想定しておくことで、安心感につながった。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の記載内容は、2025年4月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。