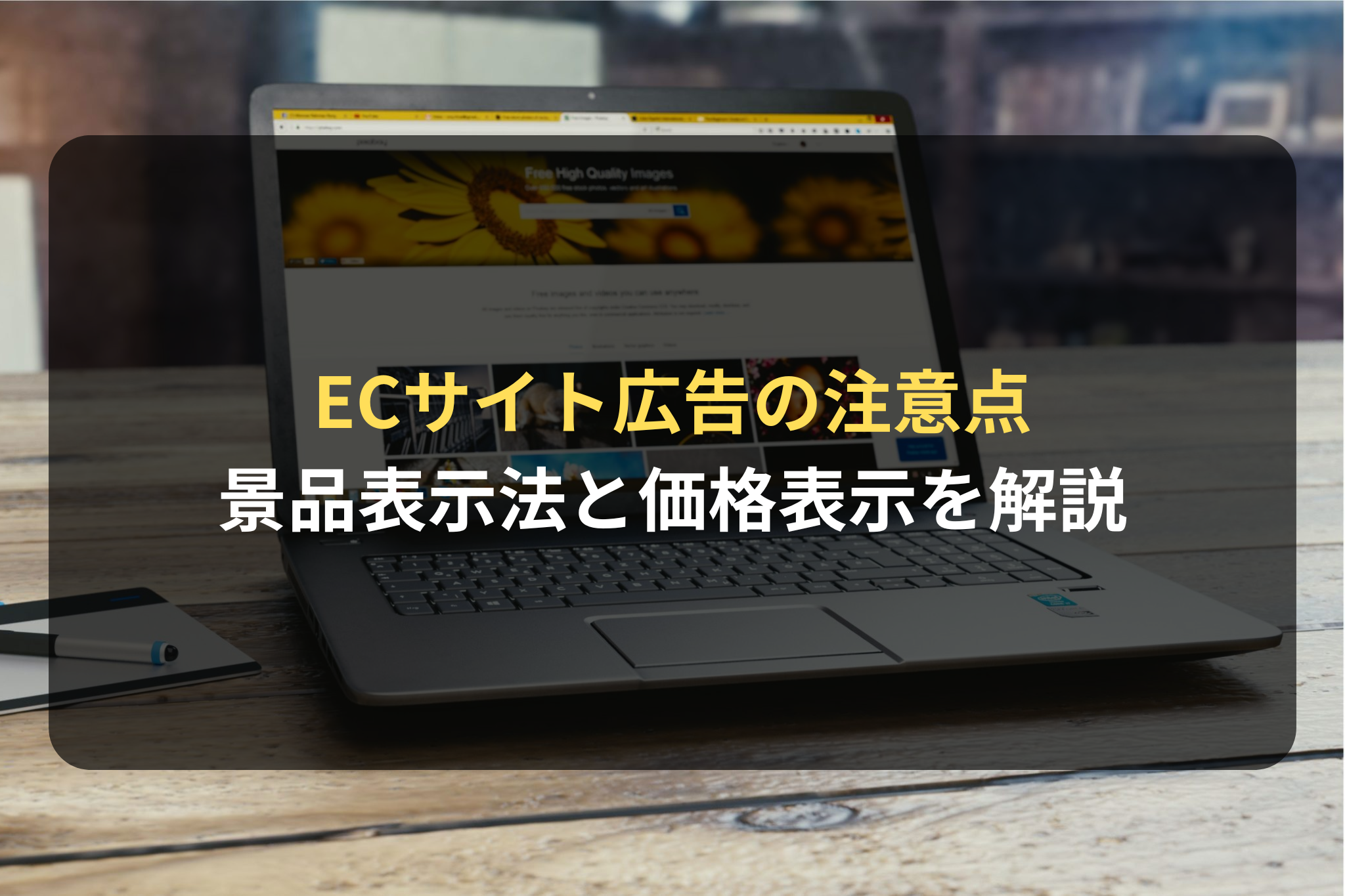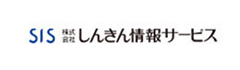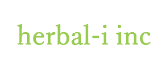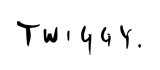EC・通販サイト運営で注意したい景品表示法とは?ポイントを解説
通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを運営している企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「景品表示法に違反しないように、商品の良さを最大限に訴求する方法はないだろうか?」
「社内のコンプライアンス意識の向上のためには、どのような取り組みをすればいいだろうか?」
「SNSで口コミを投稿したユーザーに対してプレゼント企画を実施したいが、景品はどのような基準で選べばいいか?」
「どのような商品の紹介の仕方が景品表示法に違反してしまうのか?」
この記事では、ECサイトの運営における景品表示法と価格表示について、EC専門の弁護士が詳しく解説します。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
目次
景品表示法とは
景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、実際の商品や景品の質よりも優良であるように見せる表示や過大な景品の提供を規制する法律です。
消費者は実際の商品の質よりも優良であるように見せられたり、過大な景品を提供されたりすることによって、自主的且つ合理的な商品選択ができなくなってしまう可能性があります。景品表示法の目的は、不当な商品の表示方法による消費者の自主的かつ合理的な商品選択の阻害を防止し、一般消費者の利益を保護することなのです。
過大な景品類の提供の禁止
景品表示法で定められていることの一つに、過大な景品類の提供の禁止があります。景品を提供することは消費者にとって一見利益があるように思われますが、景品とは消費者を誘引する(引き寄せる)ために提供するものです。過大な景品を提供することで、本来商品の購入を考えていない人まで引き寄せることになり、消費者による自主的かつ合理的な商品選択を阻害すると考えられるのです。たとえば、クーポン付与のキャンペーンを実施する場合や、口コミを紹介した購入者にお礼の品を送る場合などにも注意が必要です。
景品表示法で規制されている景品には、一般懸賞、共同懸賞、総付景品(ベタ付け景品)の3点があります。以下、順に紹介します。
一般懸賞
商品を購入した消費者に対して、くじやクイズで景品類を提供する懸賞の中で、共同懸賞以外のものを一般懸賞といいます。
一般懸賞で提供する景品類では、限度額が以下のように定められています。
◆ 懸賞による取引の価額が5,000円未満の場合:
・提供する景品類の最高額は取引価額の20倍
・景品の最高総額は懸賞に係る売上予定総額の2%
◆ 懸賞による取引の価額が5,000円以上の場合:
・提供する景品類の最高額は10万円
・景品の最高総額は懸賞に係る売上予定総額の2%
懸賞による取引の価額というのは、いくらの商品を購入したかということです。具体例を挙げると、1,000円の商品を購入した場合、懸賞に当たってもらえる景品の最高額は、1,000円の20倍の、2万円以下である必要があります。さらに、商品の売上予定総額が200万円の場合、提供できる景品の総額は最大で4万円までとなります。この限度額を超える景品を提供すると、法律違反となるため注意が必要です。
共同懸賞
市町村などの地域や、複数の事業者が参加して行う懸賞を共同懸賞といいます。商店街で行われる懸賞などがこれに当たります。共同懸賞では、提供する景品の最高額は取引価額にかかわらず30万円と定められています。また、景品の最高総額は売上予定総額の3%までと定められています。
総付景品(ベタ付け景品)
懸賞ではなく、商品の購入者やサービスの利用者にもれなく提供する景品類を、総付景品といいます。先着順など、数量等の制限を設けたものも総付景品に該当します。総付景品にも限度額が定められており、具体的には以下の通りです。
◆ 懸賞による取引の価額が1000円未満の場合:
・提供する景品類の最高額は200円
◆ 懸賞による取引の価額が1000円以上の場合:
・提供する景品類の最高額は取引価額の10分の2
規制の対象にならない懸賞
懸賞の中には、景品表示法の規制の対象にならない形もあります。それがオープン懸賞と呼ばれるものです。オープン懸賞は、景品表示法の規制の対象となる一般懸賞・共同懸賞・総付景品とは異なり、商品の購入やサービスの利用といった取引を条件としていない懸賞です。たとえば、テレビやWebサイトなどで企画を告知し誰でも応募できるものです。このようなオープン懸賞においては、景品規制は適用されません。
不当な表示の禁止
EC・通販サイト運営で特に重要となるのは、景品表示法の中でも不当な表示の禁止に関する規制です。サイトで販売する商品やサービスが、実際よりも優れている・お得だと誤解させる表現を規制しています。
また、景品表示法で規制される表示は、消費者が不利益を被る可能性がある表示について広く該当します。具体的には以下のとおりです。
- 店舗の看板
- 商品のパッケージ
- チラシやカタログ
- 訪問や電話のセールストーク
- 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等の広告 など
また規制される表示には、優良誤認表示と有利誤認表示があります。次項で詳しく解説します。
インターネット広告で気を付けるべき「優良誤認」と「有利誤認」
優良誤認とは
優良誤認表示とは、実際に販売する商品よりも著しく優良なものである、または競業他社の製品より著しく優良であると誤認させる表示をいいます。優良誤認表示となるのは、主に品質や規格の不当な表示です。具体的には、品質や規格を偽装して、実際の商品・サービスよりも優れていると見せかけるものです。
◆ 品質(商品に関する成分や属性)に関する優良誤認表示の例:
・実際には添加物を使用している食品に対して、添加物不使用と表示して販売した。
◆ 規格(国、公的機関、民間団体などが定めた一定の要件)に関する優良誤認表示の例:
・実際には日本工業規格に定められた明るさに足りていない電球に対して、規格を満たした明るさであると表示して販売した。
◆ その他(原産地、製造方法、受賞の有無、有効期限など)に関する優良誤認表示の例:
・実際にはブランド牛ではない牛肉に対して、有名ブランド牛と表示して販売した。
優良誤認表示とされるのは著しく優良であると誤認させる表示ですが、著しくとは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていることとされています。つまり、優良誤認表示に当たるかは、商品の性質や一般消費者の知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容などをもとに、表示全体から判断されることになります。
有利誤認とは
有利誤認表示とは、商品価格や取引条件が実際より有利である、または競業他社と比べ著しく有利であることを誤認させる表示をいいます。有利誤認表示となるのは、主に価格や取引条件の不当な表示です。具体的には、価格や取引条件に関して、実際の商品・サービスよりも優れていると見せかけるものです。この場合の取引条件とは、数量・アフターサービス・保証期間・支払い条件などです。具体的に有利誤認表示に当たる表現としては、以下のような例があります。
◆ 有利誤認表示の例:
・常に同じ値段で販売しているにも関わらず「限定○名様」「先着○名様のみ」と表示する
・「○月限定のキャンペーン」など期間限定を謳った広告を通年で掲載し続けている
有利誤認表示に当たるかどうかの判断基準は優良誤認表示同様に、著しく有利であることを誤認させる表示をしているかどうか、表示全体から判断されることになります。なお、故意に偽って表示した場合だけでなく、誤って表示してしまった場合も有利誤認表示にあたる点に注意が必要です。
また、二重価格表示も表示の方法によっては、有利誤認表示に当たる可能性があります。有利誤認表示に当たるEC・通販サイトの価格表示に関しては、次項「3.価格表示に関する消費者庁のガイドライン」で詳しく解説します。
内閣総理大臣が指定する消費者の誤認を招くおそれがある表示
優良誤認表示や有利誤認表示だけでは、消費者の自主的かつ合理的な商品又はサービスの選択を妨げる表示に十分に対応することできない場合があるため、消費者庁の主任の大臣たる内閣総理大臣に、不当表示を指定する権限が付与されています。2025年2月時点では、内閣総理大臣が指定する消費者の誤認を招くおそれがある表示として以下の7つの表示が定められています。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
- 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
・EC企業に重要な景品表示法とは?ルール、違反事例、ペナルティを弁護士がわかりやすく解説
- 不実証広告規制とは?
-
優良誤認表示を効果的に規制するため、消費者庁長官は、優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、当該表示は、措置命令との関係では不当表示とみなされ(第7条第2項)、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定されます(第8条第3項)。
出典:「不実証広告規制」(消費者庁)
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/
misleading_representation/not_demonstrated_ad/)提出資料が合理的な表示の裏付けであるといえるためには、①提出資料が客観的に実証されたものであること、②提出された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが求められます。たとえば、美容液の販売においてシミ予防効果を謳った場合には、・シミを予防する効果について、専門機関等の実証実験を行う、・シミ予防効果が実証実験の結果で証明されていること、が考えられます。また、実証実験を行っていたとしても、期間内に資料を提出できなければ、シミ予防効果に関する表示は不当表示とみなされてしまうため、客観的なデータや資料は適切に保管しておくことをおすすめします。
①の客観的に実証の考え方についてまとめましたので、ご活用ください。
・試験調査によって得られた結果
試験や調査の方法は、表示の対象となるものに関連する学術界、産業界において、一般的に認められた方法または関連分野の専門家の多数が認める方法であることが必要です。消費者の体験談やモニターの意見等については、特定の者や少数の者の意見ではなく、相当数のサンプルを用意し、そこから不作為に意見を選ぶ等、客観性を確保することが重要です。
・専門家、専門団体もしくは専門機関の見解または学術文献
専門家が客観的に評価した見解または学術文献であって、その専門分野において一般的に認められている必要があります。
価格表示に関する消費者庁のガイドライン
EC・通販サイトであるか否かにかかわらず、商品やサービスを販売する上で、販売価格や取引条件を偽って表示してはいけないのは当然のことです。ただし、実際にどのような表現をすれば優良誤認表示や有利誤認表示になるかの判断はなかなか難しいものです。なぜなら、それが著しく消費者に不利益を与える表現かどうかは、前述のとおり、表示全体から総合的に判断されることになるためです。
特に、価格表示に関しては有利誤認表示になってしまう可能性があるため、より注意深く対応する必要があります。価格表示に関して具体的に消費者庁の方針を知ることができるのが、消費者庁が公表している「不当な価格表示についての景品表示法の考え方」というガイドラインです。ガイドラインの中で、価格に関する有利誤認表示は、以下のように3つに分類されています。
- 実際の販売価格よりも安い価格の表示
- 他の価格と比較することによりその商品の販売価格が安いとの印象を与える表示(二重価格表示)
- その他、販売価格が安いとの印象を与える表示
EC・通販サイトを運営する際は、このガイドラインを必ずチェックしておく必要があります。
問題となる価格表示
実際の販売価格よりも安い価格の表示
商品ページに販売価格が表示されていれば、消費者は当然表示されている価格で商品を購入できると考えます。そのため、販売価格を実際より安く表示することはもちろん有利誤認表示に当たります。
それ以外にも、その価格が適用されるための条件等がある場合は、それも正確に表示する必要があります。以下のケースは、有利誤認表示にあたり景品表示法違反となります。
- 表示価格では、商品やサービスの一部しか享受できない
- 表示価格で購入するためには、別の商品の購入などの条件がある
二重価格表示
二重価格表示とは、他の価格を比較対象に表示して、商品の安さをアピールするものです。メーカー希望小売価格や過去の実際の販売価格など、事実を元に表示する場合は二重価格表示も認められますが、有利誤認表示にあたるケースも多いため注意する必要があります。以下の二重価格表示のケースは、有利誤認表示にあたり景品表示法違反となります。
- 販売実績のない過去の価格を比較対象としている
- セール直前に一時販売しただけの過去の価格を比較対象としている
- 販売することが確実でない将来の価格を比較対象としている
- 偽りのメーカー小売り希望価格を比較対象としている
- 偽りの他社の販売価格を比較対象としている
- 他者への販売価格を比較対象とし、自分だけが安く買えると誤解させている
- 実際より販売価格が安い印象を与える表示
価格の安さや値下げを強調するために、安さの理由を示して、販売商品のすべてが安くなっているようにアピールすることがあります。安さをアピールしているにもかかわらず、通常に比較して特に安くなっていない、または値下げが一部に限定されている場合には、有利誤認表示となるおそれがあります。以下のようなケースでは、有利誤認表示となるおそれがあるため注意が必要です。
- 割引率を表示しているが、一部の商品のみが対象で他の商品は割引されていない場合
- 期間限定セールをアピールしているが、通常価格より安くなっている商品がごく一部の場合
インターネット広告の表示のお悩み、リスク、課題は解決できます
この記事では、ECサイトを運営する企業の皆さまが、自社の製品を消費者にアピールする際に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスや製品へのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、EC事業における広告表示、広告運用についての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「景品表示法を守りながら、商品やサービスの良さを消費者にアピールすることができる。」
「インターネット広告のリスクについて事前に相談ができ、適切な広告を行うことで、消費者や社会からの信頼を得ることができる。」
「顧客トラブルや法的リスクを低減し、安心感を持って事業を拡大することができる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「自社の商品やサービスの表示を事前に精査してもらえて、表示が違反行為に該当していないことを確認でき、自信をもって販売することができるようになった。」
「研修を通して、従業員の景品表示法に関する理解が深まり、コンプライアンスの仕組みづくりを導入することができた。」
「インターネット広告にかかわらず、ビジネスを行う上で直面するさまざまな不安を気軽に相談できたので、本来の業務に集中して取り組むことができた。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
こちらから「メールでスピード相談」ができます。
※本稿の記載内容は、2025年2月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。