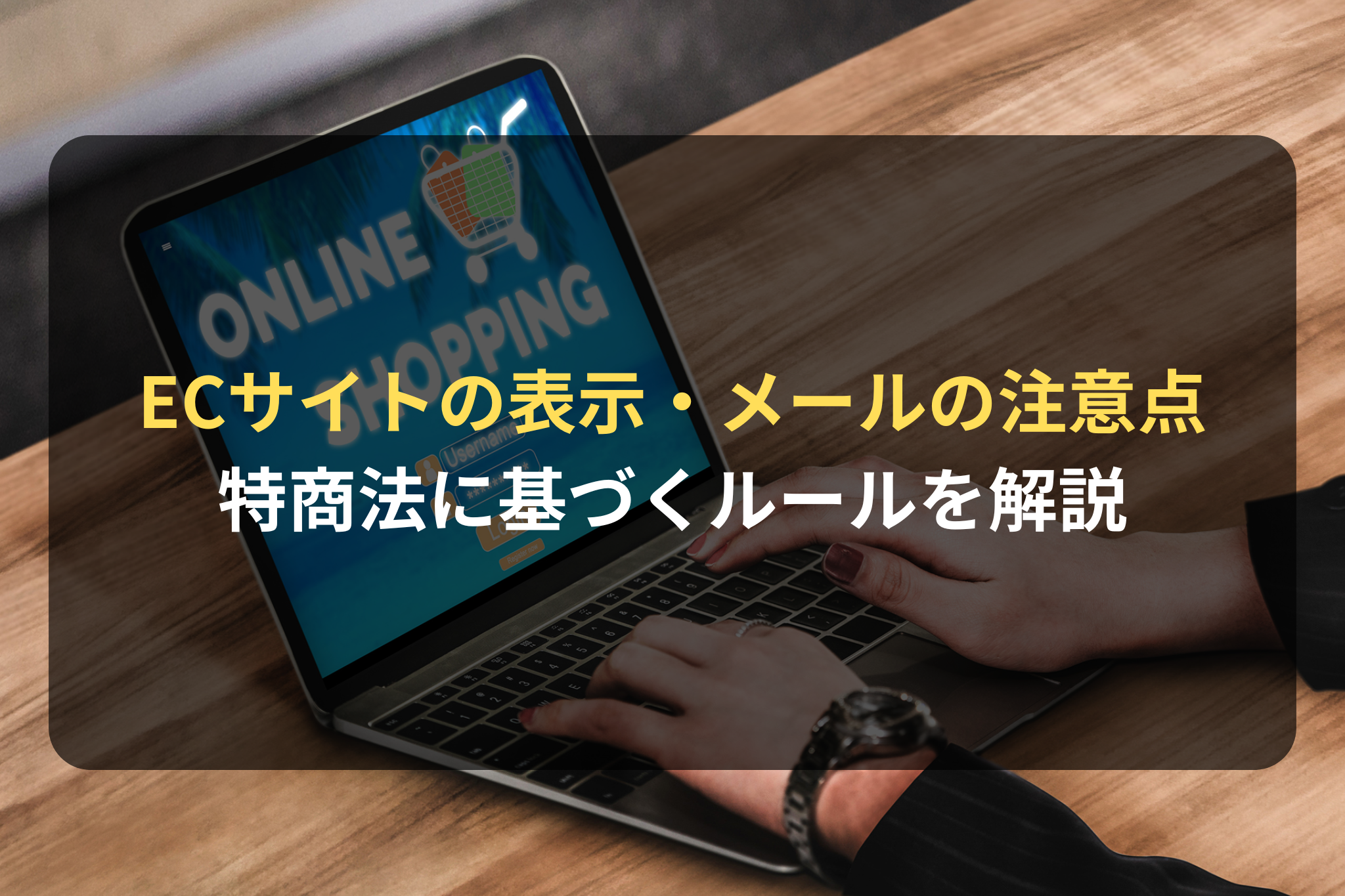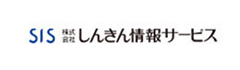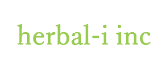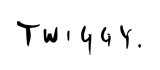通販サイトやオンラインモールなどのECサイトの運営をしている企業の担当者の皆さまは、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「特定商取引法という法律があるのは知っているが、具体的な内容についてもっと知りたい。」
「ECサイトにおける表示について、きちんと表示ができているのか、法律違反になっていないだろうか。」
「販促活動の一環として、顧客に電話やメールで連絡を取りたいがどのようなことに注意したらいいだろうか。」
この記事では、ECサイトを運営する際に注意したい、特定商取引法(以下、「特商法」といいます。)に基づく表示とメールのルールについて、EC専門の弁護士が詳しく解説します。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
目次
特定商取引法(特商法)とは何か
特商法の基本情報
EC・通販サイトを運営するためには、サイト上で特商法に基づく表記について記載する義務が生じる場合があります。また、特商法の対象は電子メールにも及びます。特商法に基づく表記とは具体的にはどのようなものなのか、EC・通販サイト運営に関係する特商法について解説します。
特商法とは、正式名称を「特定商取引に関する法律」といい、取引の公正性と消費者被害の防止を図るための法律です。商品の売買において弱い立場に立つ消費者を守り、また販売者を明示することで商品の流通や提供を明確化していくためのものです。
日本の高度経済成長期に、訪問販売やマルチ商法など販売業者と消費者(個人)とのトラブルが増加し始めました。特商法は、それらのトラブルを改善し消費者を守るために昭和51年に施行された法律です。具体的には、事業者が厳守すべきルールやクーリング・オフなどの消費者を保護するルールについて定めています。特商法の対象となる取引の種類は、以下の7つです。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
EC・通販サイトは上記類型の中の通信販売に該当します。そのためECサイト運営者は、特商法が定めるルールのうち、通信販売に関するものを厳守する必要があります。
特商法に基づく表記とは
EC・通販サイト等、特商法の対象となる取引においては、特商法に基づき、一定の事項を必ず表示しなければなりません。これを特商法に基づく表記と呼びます。
表記は法律上義務付けられるものですが、消費者心理としても情報を開示してくれているサイトの方がより信頼できると考えられます。特商法に基づく表記があることで、消費者は安心して買い物をすることができます。消費者の立場からすると、何の情報もない事業者から商品を購入するのは不安です。その不安を払しょくするための情報として、特商法に基づく表記が必要なのです。
EC・通販サイトにおいては、特定商取引法に基づく表記というページを設定し、以下の内容を記載する必要があります。
- 事業者名
- 所在地
- 連絡先
- 商品等の販売価格
- 送料などの商品代金以外の付帯費用
- 代金の支払時期
- 代金の支払方法
- 商品等の引き渡し時期
- 返品の可否と条件
それぞれの項目の具体的な表記内容について、次項で詳しく解説します。
特商法に基づく表記の表記方法
特商法では、EC・通販サイトの取引類型は通信販売に該当します。特商法では2022年6月の改正によって、通信販売に関する規制拡大の一環として、EC事業者が表示を義務付けられる事項が追加・拡大され、現在では以下のように定められています。。
第11条(通信販売についての広告)
「販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
五 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項」
具体的にはどのような表記が必要なのか、以下にご説明します。
事業者名
事業者の名称を記載します。この場合の名称とは、登記簿上に記載されている正式な名称であることが必要です。さらに、代表者もしくはEC・通販サイトの責任者の氏名を記載する必要があります。
所在地
事業者が現在使用している住所を記載します。また住所を記載する際は、省略せず正式な住所を記載する必要があります。
連絡先
消費者からの問い合わせに対応するための連絡先を記載します。具体的な指定はありませんが、電話番号に合わせてメールアドレスも記載するケースが多いです。また問い合わせに対応できる曜日や時間帯を記載すると親切です。
商品等の販売価格
販売する商品の販売価格を記載します。扱う商品が多い場合は商品紹介ページをご参照くださいと記入し、そちらに販売価格の表示をリンクすることも可能です。ただし、定価や希望小売価格等だけではなく、実際の販売価格を記載することが義務付けられています。
送料等の商品代金以外の付帯費用
消費者が負担しなければならない費用について、具体的な金額を記載します。この場合の費用には、送料や振込手数料、代金引換手数料などが該当します。表示した販売価格に対して、消費税が別途必要な場合もここに記載する必要があります。
代金の支払時期
消費者が商品を購入する際に、代金を支払う時期(タイミング)を記載します。大きく分けて、前払い、後払い、同時払い(代引き)があります。具体的には、以下のように記載します。
- 前払いの場合:代金入金確認後、即時(または○日以内)に商品を発送致します。
- 後払いの場合:商品到着後、同封の振込用紙にて〇日以内にお振込みください。
- 代金引換の場合:商品到着時に、運送会社に代金をお支払いください。
代金の支払方法
対応している支払い方法について記載します。支払方法には以下のようなものがあります。
- クレジットカード決済
- 銀行振込み
- 代金引換
- コンビニオンライン
- コード決済(Apple Pay/LINE Pay等)
- 電子マネー(Suica等)
商品等の引き渡し時期
商品を注文してから、商品が届くまでにかかる時間を記入します。ただし、消費者の手元に商品が届くまでにかかる時間は運送状況にも影響されるため、基本的には、入金確認後○日以内で発送致します、という表記の仕方が考えられます。
返品の可否と条件
注文商品の返品の受付可否や、返品に関する特約など記載します。ここに記載するのは、商品に欠陥があった場合などではなく、商品に問題はないが消費者の都合で返品したいという場合のルールです。
特商法(15条の3第1項)によると、通信販売ではクーリング・オフ制度とは別に、商品を受け取って8日間までは返品できるという規定が存在します。ただし、返品の可否と条件を表示していればそちらが優先されるため、このルールは適用されません。
- 特商法に基づく表記のうち、省略できる表記とは?
-
特定商取引法第11条には通信販売についての表示義務について規定されていますが、但書には以下のように書かれています。
「ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。」
サイトの運営にあたり、広告スペースは限られており、すべての表示が難しい場合もあるかと思います。一例ですが、省略できる事項のポイントは下記の通りです。
- 請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示、があること:
消費者からの請求により、特商法に基づく表記(事項)が記載された電子メール等を提供することが表示されていることが必要です。たとえば、請求がある場合には、(省略した事項が分かるカタログや資料)を電子メールで送信致します、と表示する方法です。明確な決まりはありませんが、消費者にとって分かりやすいような記載の仕方が望ましいです。 - 販売価格、送料等についての事項は、一部のみを表示することはできない:
販売価格、送料等購入者の負担すべき金銭は、購入者が誤解をし、不利にならないよう、全部を表示しない方法しか選択できません。 - 省略できない事項一覧:
①契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
②返品に関する事項(返品の可否・返品の期間等条件・返品の送料負担の有無)
③ソフトウェアを使用するための動作環境
④契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件又は提供条件
⑤販売数量の制限等特別の販売条件又は提供条件があるときは、その内容
⑥請求により交付する書面又は提供する電磁的記録が有料のときは、その額
⑦(電子メールで広告するときは)電子メールアドレス
出典:「特定商取引に関する法律の解説(逐条解説)」(特定商取引法ガイド)
(https://www.no-trouble.caa.go.jp/law/h28.html)
たとえば、消費者から承諾や請求がないにもかかわらず広告メールを送り、そのメールで省略できない事項について省略をしてしまったようなケースでは注意が必要です。消費者との間の公正な取引を著しく阻害し、消費者の利益を侵害するような極めて悪質なものであると認定された場合には、1年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科される(特商法第72条2項)ほか、指示(同法第14条) や業務停止命令(同法第15条)等の対象となる可能性があるためです。
- 請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示、があること:
法律の規制対象となるメールはどのようなものか
広告メール送信時に知っておくべき特商法と特定電子メール法
メールにて広告を行う際には、特商法と特定電子メール法、2つの法律による規定を守る必要があります。
特商法とは、消費者の利益を守るための法律です。特商法については上記で解説しましたので、次に特定電子メール法についてご説明します。
特定電子メール法は、営利目的で不特定多数宛てに配信される迷惑メールを防止するための法律です。この特定電子メール法が適用される電子メールを、特定電子メールといい、広告宣伝のために送信するメールがこれに該当します。また、SMSを利用して送信されるものも特定電子メールにあたります。
特商法と特定電子メール法で定められる内容
まず特商法では、以下のルールを守る必要があります。
- 事前にメールを送信する相手の同意を得る(オプトイン方式)
- 同意を得られた場合は、同意を得た証を記録
- 承諾(同意)があったことを示す書面または電子データを保管
- データの保管期間は、対象の電子メール広告を最後に送信してから3年間
- 送信メール内に、配信を拒否するための方法をわかりやすく記載
次に、特定電子メール法のルールを紹介します。
- 事前にメールを送信する相手の同意を得る(オプトイン方式)
- 同意を得られた場合は、同意を得た証を記録
- 同意を得た証の記録期間は、対象のメールを最後に送信してから1か月以上
- 送信メール内に、定められた情報(送信者情報など)の記載を行う
2つの法律のルールはよく似ていますが、ポイントは以下のとおりです。
- 共に、事前にメールを送信する相手の同意を得る(オプトイン方式)
- 記録・保管義務の対象は、特定電子メール法では同意を得た証なのに対し、特商取法では加えて承諾があったことを示す証拠のデータが必要
- 保管期間は、特定電子メール法では1か月以上なのに対し、特商法では3年
- 送信メール内に記載すべき内容は、特定電子メール法では定められた情報なのに対し、特商法では配信を拒否するための方法
広告メールを送信する際には、2つの法律両方のルールを守ることができるよう、各項目について厳しい方の条件に合わせて行う必要があります。
・ECサイトの運営において、法令上、事業者が準備しておくべきこととは?最低限、サイト上に必要な記載・表記を解説
メール送信には事前同意が必要
前項でも紹介したように、広告メールを送る際は、原則として事前に受信者の同意をとる必要があります。
以下では、同意を取得する方法や同意の範囲について解説します。
事前同意の取得方法・同意の範囲
広告メールを送信することに対する同意を得るためには、受信者に広告・宣伝メールの送信が認識されるように説明し、受信者が承諾の意思を表示する必要があります。
具体的な方法としては、商品の購入ページや会員登録ページの申込みボタン付近に、広告メールの受信の希望に関するチェックボックスを設けるとスムーズです。利用者にチェックを入れてもらう方法であれば、広告メールを送信する承諾を得たといえます。
事前に同意を取得しておかなければならない範囲は、広告メールを送信することであるため、メールの種類や内容までは指定する必要はありません。ただし注意点として、メールの送信者が誰かを認識してもらった上でないと同意を取得したことになりません。そのため、送信者の名称等をわかりやすく記載し認識できるような状態で同意を得る必要があります。
メール送信時のポイント
前述の各法律のルールの箇所でご説明したとおり、広告メール送信時には、特商法と特定電子メール法において定められた一定の事項を記載する義務があります。以下に、メールに記載が義務付けられている事項について具体的に列挙します。
- 特商法:
- 配信を拒否するための方法(配信停止の手続き方法)
- 特定電子メール法:受信者が事前の同意を通知しているメールであることが容易に判断できるように、下記の項目を表示する必要があります。
- 送信者の氏名または名称
- 受信拒否ができる旨の通知
- 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
- 送信者の住所
- 苦情や問い合わせの受付先
参照:「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」(総務省)
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf)
ECサイトの表記についてのお悩み、リスク、課題は解決できます
この記事では、ECサイトの開設を考えている、ECサイトの運営をしている企業の皆さまが、ECサイトの表記や広告メールについて直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、EC事業における広告表示、広告運用についての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「自社のECサイトを見直して、法的なリスクのある表記を修正することができる。」
「法令を守ることで、消費者から信頼されるECサイトを運営していけるようになる。」
「商品画面の作成やクレーム対応など、ECビジネスに関するありとあらゆる心配やリスクを低減することができる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「自社では拾いきれないリスクを提示してもらい、より安心して事業を進められるようになった。」
「特商法や関係する法令についての研修を通じて、従業員の理解が深まり、社内の遵法意識やリスク管理に対する意識が向上した。」
「分からない点や不安な点はすぐに質問できたので、集客や販売数を増やすための業務に集中することができた。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
こちらから「メールでスピード相談」ができます。
※本稿の記載内容は、2025年2月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。